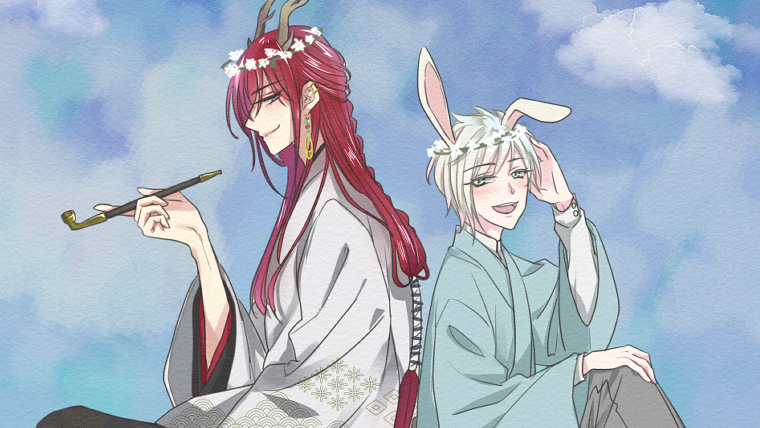ブループリントシンデレラ

自分の肌の色も、目の色も、髪の色も、大嫌いだった。
何でこんな風に産まれたんだろう。神様は不公平だ。ずっとそう思ってた。
人より劣っている自分を、どうにかして隠したかった。変えたかった。
……でも本当は逆だった。
ただそのままを好きになってあげたかった。
何も変えない自分を認めてあげたかった。
この姿を選んで生まれて来た俺に、誇りを持ちたかったんだ!!
(心の弱さと劣等感を抱えた一人の男の子が、勇気を出して目を覚ましていくまでの物語)
自分が大嫌いで、隠したくて、でもキラキラしてる他人が羨ましくて、妬ましくて。そんな心の弱さと劣等感を抱えたユキちゃんが、勇気を出して目を覚ましていくまでの物語です。
出会い
日課である毛染めの待ち時間を潰すため、なんとなく眺めていた動画投稿サイト。そこでたまたまオススメに上がってきたのは、一人の男性アイドルのライブ動画だった。
普段アイドル関連の動画なんて全く見ない俺に、何故オススメしてきたのかは不明。けどサムネイルのデザインが良かったから、何の気無しにタップした。
(……何コイツ。なんかウザ)
スマートフォンの画面内で、自信満々にウインクと投げキスをきめるド派手な赤髪を見て、最初に沸いてきたのはただの嫌悪感だった。
ソイツはホールを埋め尽くす大観衆の中、長い手足を存分に使って、赤い髪をたなびかせ、黄色い声援を一身に受けて、気持ち良さそうに広いステージを謳歌していた。何だかそれが、俺にとってはすっごくムカついたのだ。
『#一色紅』
ハッシュタグでこのアイドルが誰なのかを知る。ふーん。そう言えばテレビで結構聞く名前かも。これがその人だったのか。それなりに有名っぽいけど、男のアイドルとか興味ないから全然知らなかった。
さらにコメント欄に目を移す。かっこいい。最高。美しい。神様みたい。生きててくれてありがとう。一生推します。あなたが居るだけで明日も頑張ろうと思える。愛してる。一色紅に対しての賞賛のコメントは、どれだけ下までスクロールしていっても途切れる事はない。
そこまで格好良いかな? 派手なだけで普通じゃん。っていうか熱量高すぎてなんか宗教みたい。コワ。たかがアイドルにここまで入れ込む人って何考えてんだろ。
『愛してるぜ♡』
決め台詞と共に画面いっぱいに表情が切り取られ、歓声が爆発する。その瞬間、俺の胸の袂もぞわりと震えた。
何なのこいつ。ほんっと気持ち悪い。イラつく。見てらんない。こんなに自信満々で恥ずかしくないわけ? 自分の事そんなに恰好いいと思ってんの? 心の中を、どろどろと、醜い感情が支配する。
でも、そんなにイラつくなら見るのをやめればいいだけの話なのに
何故か俺は、その動画から目が離せなかった。
「ユキー! まだ髪洗わなくていいのー? 学校遅れるよー!?」
映像に釘付けになっているうちに、放置時間を随分過ぎていたらしい。階下から呼ぶお母さんの声ではっと我に返る。「分かってる!」全然分かってなかったくせに反射的にそう言って、スマホを伏せてお風呂場に急いだ。
洗い場で、頭を下に向けてシャワーを浴びる。真っ黒になったお湯が、排水溝に吸い込まれていく。二週間に一回見る光景。小学生の頃からずっと。初めはお母さんにやってもらっていたけど、いつからか自分でも出来るようになって、もう随分と慣れたもんだ。このお湯の色にも、何も感じなくなった。
脱衣場に出て鏡を見る。髪を掻き上げて根元を確認。うん。ちゃんと染まってる。白くない。
(……でもそろそろまた、毛先まで染めなきゃ)
色の抜け始めた毛先を触ると、ぎしりと指通りの悪い感触があった。何度も、何度も、頻繁に毛染めを繰り返すうちに、痛んでボロボロになってしまった。でもしょうがない。俺の髪は小さい頃からこんなもんだ。
リビングに戻って、髪の毛を乾かしながら、朝の小テスト範囲のノートを今更眺める。テレビでは、全国的にお日様マークがついた今日の天気予報が流れている。トーストと目玉焼きのいい匂いが香ってくる。
「ねぇユキ。そろそろ髪染めるのやめたら? いい加減大変でしょ」
朝ごはんの準備をしていたお母さんが、背中越しに声をかけてきた。
「別に。大変じゃないよ」
「……お母さん、ユキの髪の色好きなんだけどなぁ」
その言葉に、心が少しだけ痛くなった。でも、一瞬だけだ。なんてことない。
「……だって俺はこの色の方が好きだもん。普通だし」
ぱちん。ドライヤーを切って、髪をとかす。お母さんは「そっか」ってちょっと寂しそうに相槌を打って、それ以上何も言わなかった。
俺は生まれつき、体全体の色素が薄かった。
肌は抜けるように白く、瞳の色は薄い水色で、髪は銀とも金ともとれない淡いプラチナブロンド。まだ自分の世界が、血のつながりがある家族だけで完結していた頃は、周りの大人たちはその容姿を凄く褒めてくれた。綺麗。可愛い。天使みたいって。
だけど幼稚園に通い始め、一気に世界が広がった時、俺は自分の容姿が皆とは少し違う事を知った。肌の色も、髪の色も、こんなに淡い子は一人も居なかった。当然どうやったって悪目立ちするし、皆の好奇の視線の的になる。
何でそんなに白いの? 何でおばあちゃんと同じ髪の色してるの? ユキは白くて弱そうだから戦いごっこに入れてあげない。極めつけは
『ユキ君て、まっしろでオバケみたいでコワイからきらい』
ちょっと可愛いなって思ってた女の子から、そう言われて逃げられてしまった。
ああ、俺って変なんだ。このままじゃ嫌われちゃうんだ。幼稚園という初めての社会生活で、俺は自分がマイノリティだという事実を学んだ。だったら少しでも普通に、皆に嫌われないようにするために、出来る事をやるしかない。
以降、小学校に上がる頃からずっと、髪を黒く染め続けている。
その日学校では、文化祭の演劇の配役を決めるクラス会議があった。
「やっぱり王子様役はハヤト君でしょ!」
真っ先に主役へと名前が挙がったのは、クラスで一番目立つ男子。勉強が出来て、運動も出来て、背が高くて、やけに大人っぽくて、いつも話題の中心で、当然女子からもモテる。そんな、一学年に一人だけ特別に居るような、まさに王子様みたいな子だ。
「あっ、分かる~!」
「カッコイイし華があるよね」
「衣装も絶対似合うと思う!」
黒板の前に立つ委員長と、王子様役に推薦する女の子達の会話を、俺は蚊帳の外でぼうっと聞いていた。だって俺には関係のない事だから。
反対意見なんて出るはずもなく、本人もやるよって感じで、あれよあれよと話はまとまっていった。あーこれ、お姫様役すっごい取り合いになりそう。皆絶対やりたいでしょ。そんな事を考えて頬杖をついていると、それまで黙っていた一人の女子が、おずおずと手を上げた。
「あ、あの……あたし、ユキ君も、いいんじゃないかなって思うんだけど……」
その瞬間、クラス全員の視線が俺に集まる事となる。何が起きたか分からず一瞬思考と動きが停止して、それからぶわりと変な汗が滲んできた。
「おっ……俺はいいよ! ハヤト君でいいじゃんっ……!」
大慌てになって顔の前でぶんぶんと手を振りたくる。だけど皆の視線が俺から外れる事はない。
「え~? でもユキ君確かに綺麗な顔してるっちゃしてるし」
「衣装着て髪の毛ちゃんとすれば案外イケるかもよ?」
「じゃあ多数決とろ多数決! ハヤト君とユキ君前出て!」
皆の前に引っ張り出されて、クラスどころか学年の王子様の隣にいきなり立たされて、どうしたらいいか分からず下を向くしかない。その間も匿名投票は着々と進み、四つ折りにした紙が教壇の上に集められた。
「じゃあ開票します! まずハヤト君一票! ……」
結果は勿論ハヤト君の圧勝。俺の倍近く。うん、最初から分かってた。
こんなの俺、完全にただの噛ませ犬じゃん。格好悪。そんな事を考えながら日直仕事の黒板消しに勤しんでいると、まさにそのハヤト君がこちらに近づいてきた。
「なぁユキってさ、何でそんなにオドオドしてんの?」
「えっ……し、してないけど……」
ハヤト君の真っ直ぐな瞳に、心の中に住み着いている劣等感を見透かされたみたいで、言葉に詰まった。っていうかそうじゃなくても、藪から棒にハヤト君の隣に立たされたら、誰だって落ち着きなくなるでしょ……。
「もっと自信もって前向いてたら、多数決俺じゃなくてユキになってたと思うけど。実際三分の一はユキに入れてたし」
「そ……そんなワケないじゃん! 何言ってるんだよ!」
「何でそんなわけないって分かるんだよ」
「えっ……だ、だって……」
何で、って言われても。
そんなの当たり前の事すぎて、理由を取り上げるまでもない事だ。
「だって俺、格好良くない、し、ハヤト君みたいに、華もないし、存在感もないし……王子様なんて、似合わないよ……」
こんな事をわざわざ自分の口で言わされて、何て惨めなんだろう。ハヤト君は何がしたいんだろう。泣きそうになった。今すぐこの場から逃げ出したかった。
顔を隠すように俯いていく俺をじっと見つめ、それからハヤト君は言った。
「ユキがそういう事にしたいだけだろ?」
と。
分かってない。全然分かってない。何も分かってない! 何も知らないクセに!!
いいよね自信が持てるように生まれて来た人は! そりゃなんだって言えるだろうさ!! でも皆がそんな風に恵まれて生まれてきてるわけじゃない!! 生まれつきどうしようもない事だってある!! 自信が持てない人だっている!! 俺みたいな人の気持ちなんて、どうせハヤト君には分からないんだ!!
「俺だって……俺だってぇ……! こんな風に生まれたかったわけじゃない!! もっと普通が良かった!! ハヤト君みたいじゃなくてもいいから、せめて普通で良かったのにッッ!!」
無意識のうちに髪と肌を掻きむしりながら、枕に顔を埋めてわあわあ泣いた。怒りとか苦しみとかやるせなさとか惨めさとか、色んな感情で心がぐしゃぐしゃで収集がつかなかった。何かを吐き出したい気がするのに、口から出るのは意味のないうめき声ばかりで、自分が何を感じているのか、本当は何に怒って何に悲しんでいるのか、それすらも良く分からなかった。
そんな風に一しきり、涙が涸れるまで泣いた。そしたらふと、朝たまたま見つけた赤髪が脳裏をチラついた。重たい心をどうにかしたくて、とにかく何かに縋りつきたくて、スマートフォンを何度かタップする。閲覧履歴を遡って今朝のURLを選択すれば、華やかなセットと照明の中、派手な衣装を着てパフォーマンスをする紅の姿が映し出された。
最高に格好良く編集されたライブ映像を見ていると、ドン底に落ちていたはずの気分が勝手に高揚した。真っ赤な髪がたなびく様子は、まるで炎が踊っているみたいで、本能的に鼓動が高鳴る。青い瞳がカメラを捉える度にまるで射抜かれているかのような錯覚に陥り、鳥肌が立って、画面の向こうの存在から目が離せなくなる。
カッコイイ。いいな。……羨ましい。一瞬は素直にそう思えた。だけどその後すぐに、自己否定と、不公平さに対しての怒りがわいてきた。
(……俺とは全然違う世界の人だ)
結局すぐに見ているのが辛くなって、スマートフォンを伏せた。
ハヤト君みたいに、生まれつきキラキラしてて、皆から注目されて、自信があって格好良くて、そういう何もかもを持って生まれた世界の人間だ。俺なんかとは全然違う。俺なんて、皆と同じになるだけで精一杯なのに。皆に置いて行かれないようにするだけで精一杯なのに。何で神様は、同じ人間をこうも違うように作ったんだろう。
『あたし、ユキ君も、いいんじゃないかなって思うんだけど』
……確かにあの一言はちょっと嬉しくて
王子様役が出来るかもって思ったら、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、心がきゅんとした。
だけど、現実なんてこんなもんだ。俺なんかがでしゃばったって恥をかくだけ。皆ハヤト君の方がいいって思う。俺だってそう思う。当然だ。皆より劣った見た目を必死に隠してる俺と、自然と目立って格好いいハヤト君。どっちが王子様らしいかなんて、多数決なんて取らなくても最初から分かり切っていた。
(いいよね、持って生まれた人は)
挙句の果てに、嫉妬して、心の中でコソコソ悪態ついて、ああ、性格までこんな感じ。
神様分かってるよ。こんな当てつけみたいな事しなくたって、よく分かってる。
俺には王子様なんて似合わない。
◇
学校祭で俺は結局、一言相槌を打つだけのリスの役になった。そしてそれからも、何も変わらず日常は続いた。学校に行って、勉強して、友達と喋って、二週間に一度髪を染める。目立ち過ぎず地味でもない、一番普通の位置でクラスに溶け込む、そんないつも通りの日常が続いた。だけどそのルーティーンに、一つだけ加わったものがある。
一色紅だ。
あの日以降、俺はあのド派手な赤髪のアイドルが、気になって仕方なくなっていた。
家族に内緒でテレビを録画して、公式非公式問わず動画を見漁って、雑誌もかかさずチェックした。
紅を見ると、凄くイライラする。自分との違いを見せ付けられているようで腹が立つ。正直、ただただ嫉妬してばかりだ。だけど俺はイライラしつつも、紅から目が離せなかった。見るとイラつくのに、つい検索をかけてしまう。見るとイラつくのに、ついテレビのチャンネルをあわせてしまう。イライラして、もやもやして、それから劣等感で泣きそうになってきて、心が掻き乱されて仕方なかった。でも不快なはずなのに、紅を追う事を止められなかった。
だって、どんなにイラついても、どんなに嫉妬しても、ひとたび紅という存在に没頭してしまえば、そんなものは泡と消えるから。
ちっぽけな嫉妬なんてぶっ飛ばすくらい、ただカッコイイ。ただ心が震える。ただ体が熱くなる。その瞬間だけは、勝手に俺の心も救われてしまう。もはやアイドルなんて言葉すら、彼を表現する物としては生ぬるく思えた。だって紅は、見ている側の人間的な思考回路全てを焼き切って、本能だけで高揚させてしまうような存在なのだ。彼の光はあまりに強すぎて、俺みたいな人間の醜い影の部分を強引に炙り出し、そして炙り出した端から、その影すらも余さず照らしきってしまう。まるで、太陽みたいなとんでもないエネルギーの塊が、人の姿に身を宿してこの世に舞い降りたかのようだった。
あの、当初はバカにしていたコメント欄の人達の気持ちが、俺にもすぐに理解出来るようになった。
この人は、紛れもなく神様だ。そうとしか表現できなかった。
だけど、そんな風に明らかにファンであるにも関わらず、俺はどうしても、素直に紅の事を好きだって認められなかった。自分の気持ちなのに自分のものじゃないみたいにずっと整理がつかなくて、家族や友達にも絶対に秘密で、ライブやグッズが気になりつつも、興味のないフリをし続けた。
男のクセに男のアイドルが好きなんて恥ずかしいっていう思いも勿論あった。でも、それ以上にみっともない本音を言うと……
こんなに何もかもを持っている人の事を、好きだなんて認めちゃったら、それこそ自分がもっと惨めになる気がしたからだと思う。
そう。つまらない自尊心が、真っ直ぐに誰かを好きだと認めて応援する邪魔をしていたのだ。


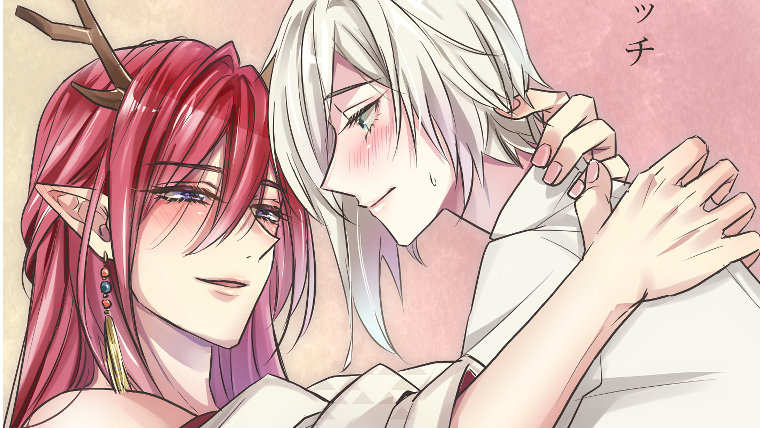
横長.png)