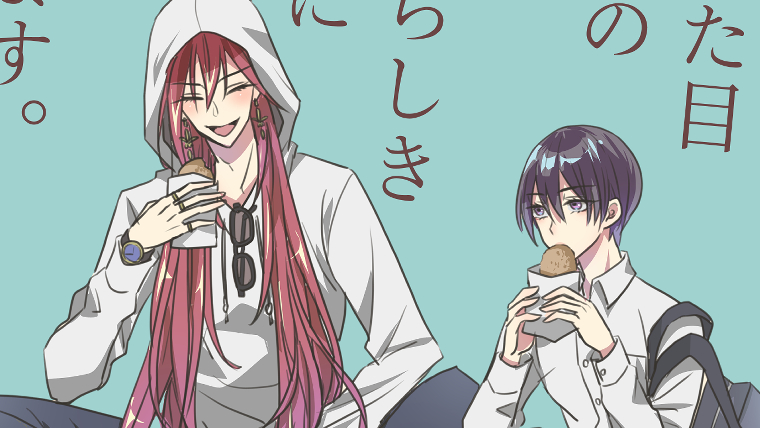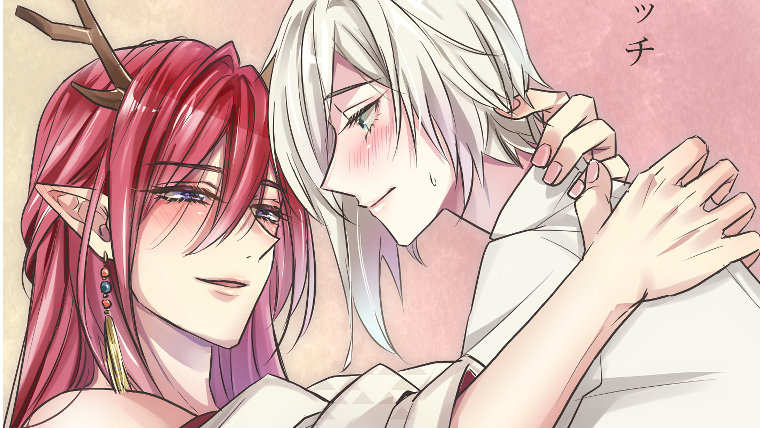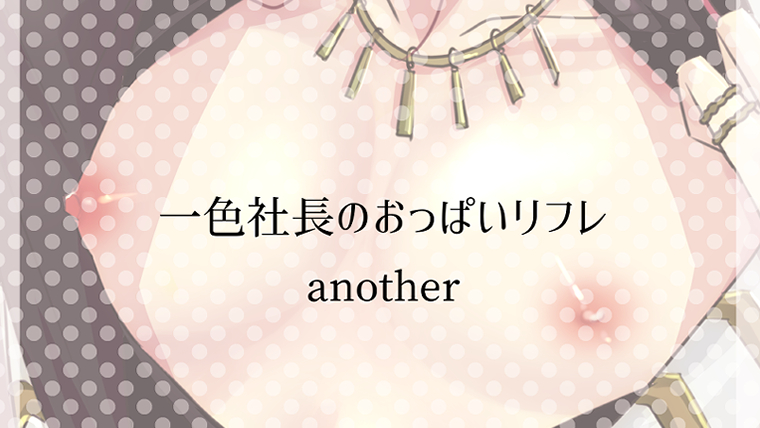ブループリントシンデレラ
変容
張り合いの無い毎日も当たり前になり始めた、ある日の事だった。
「よろしくお願いしまーす」
駅前を歩いていると、流れ作業のようにして目の前にチラシが差し出された。別にいらないけど、断るのも面倒臭いから黙ってそのまま受け取った。ちらりと視線を落とす。エンタメ系の事務所に興味ありませんかっていう、よく若い子相手に無作為にビラがばら撒かれているアレだった。
いつもは興味も持たずに鞄に突っ込んで、何日も後にくしゃくしゃになったそれに気づいてゴミ箱に捨てるようなものだった。でもその時はたまたま信号待ちが重なった事もあり、何の気なしに概要を眺めた。
『K-product所属アイドルオーディション。十歳~十八歳程度の男性。芸能活動に積極的に参加出来る方で、他事務所に所属していない方……』
ふーん。聞いた事ない事務所名。あんま有名じゃない所なのかな。
ま、どっちにしろ俺には関係ないや。そう思い、たたんで鞄に突っ込もうとした所で……下の方に記された小さな文字が目に飛び込んできた。
『代表取締役社長 一色紅』
「……!?」
え、うそ。一色紅って……あの一色紅!? うそでしょ!? 同姓同名って事!? 何の興味も無かったはずのチラシに一転してかじりつき、上から下まで入念に目を通す。信号が変わっても立ち止まったままの俺を、後ろに居たおじさんが咳払いしながら迷惑そうに追い抜いていった。
(いやでも……こんな名前の人なかなか居ないし、それ以外ない)
そういえば前に、芸能事務所を立ち上げたとかいうネットニュースをちらりと読んだ気がする。でもその時は、たかがアイドル風情が調子に乗るなとか、ファンに対して無責任に辞めたヤツに何が出来るんだとか、事業を甘く見るなとか、あちこちで物凄い叩かれ方をしていて心が痛くなった。顔も名前も出さずに知った風な口を利くこいつらは、一体どれだけ偉い人達なんだろうか。匿名で鬱憤をぶつけるような事ばっかり言う奴らの声を見る度に気分が落ち込んでしまうので、紅の事とはいえ、以降その関連のゴシップは意図的に避けるようになっていた。
(本当だったんだ)
でもそれがまさかこうやって、予想もしない形で俺の目の前に現れてくれるなんて。
(これを受ければ……会えるかもしれない……!)
興奮と喜びで手が震える。それは俺にとって一筋の光だった。表舞台から姿を消した一色紅に会えるかもしれない、千載一遇のチャンスだった。
自分がアイドルになれるなんて思っていない。ハナからそんな考えはない。ただ一色紅に会ってみたい。あの人に会わなきゃいけない気がする。あの人に一目会えたら、俺はそれだけで何か変われる気がする。
もし、最終選考まで勝ち残れば。
(紅に会える!)
そう考えただけで、体が燃えるように熱くなった。
応募書類用の写真を撮る時は、自分が一番格好よく見えるように何枚も撮り直した。人目を惹く身体づくりのために、毎日ストレッチやトレーニングをするようになった。親に頼み込んで歌とダンスのレッスンにも通わせて貰った。一色紅に会えるかもしれない。そう思う度に胸が高鳴って、オーディションを勝ち上がるためなら何でもしようと思えた。今までの人生で一番夢中で、全力で、「自分なんかどうせ」なんて、他人と比べて引け目意識を感じる暇もなかった。
どうやったらもっと格好良く見えるだろう。どうやったらもっと魅力的に見えるだろう。どうやったら目に止めてもらえるだろう。毎日その事ばかりを考えて、沢山鏡を見て、沢山練習して、自分を磨いた。
小さい頃から歌やダンスを習っていた子と比べれば、俺が今更何かした所で、ただの付け焼き刃なのかもしれない。でも付け焼き刃でも何でも良かった。出来る事があるなら少しでもいいからやっておきたかった。きっとこれは、神様が見るに見かねて与えてくれた、俺への最後のチャンスだから。
ちっぽけなプライドを守るためだけに、格好つけて、別にそんなに好きじゃないしなんて斜に構えて、全力で楽しまないで、それで俺の手元に何が残っただろう。何も残らなかった。あるとしたら、素直に応援しておけば良かったっていう、どうにもならない後悔だけだ。もう後悔だけはしたくない。もうあの時みたいなやり場のない気持ちはごめんだ。
ダサくたって、バカみたいだからって、どうせアイドルになんてなれやしなくたって、そんなのもうどうだっていい。今度こそ、全力であの人に会いに行く。
一色紅に、会うんだ。
「ねぇねぇ、ユキ君さ、最近ちょっとカッコ良くない?」
「分かる! なんか雰囲気変わったよね」
「前まで謎に自信なさそうだったんだけど、今はキラキラしてるっていうか」
「綺麗だし、なんとなく目で追っちゃうんだよね~」
そんな事を続けるうち、学校の片隅でそんな会話を耳にするようになって、最初はむず痒くて落ち着かなかったけど、でもやっぱり嬉しかった。いきなり下駄箱に手紙が入っていたり、校舎裏に呼び出されて好きですって言われたりして、そんな経験今まで一度も無かったから、驚いてどうしたらいいか分からなくなった。でも、それでもやっぱり嬉しいものは嬉しかった。
俺ってもしかして、自分が思う程悪くないのかもしれない。もしかしたら、少しくらいなら、格好いいのかもしれない。そうやって、ちょっとだけ勘違いして、己惚れて、それが少しずつ自信に変わっていった。まだ紅に会うっていう夢は叶っていないはずなのに、オーディションが進むにつれ、いつの間にか前よりもずっと、生きるのが楽しくなっていた。
自分の中で、自分の周りで、何かが変わり始めた音がした。





横長.png)