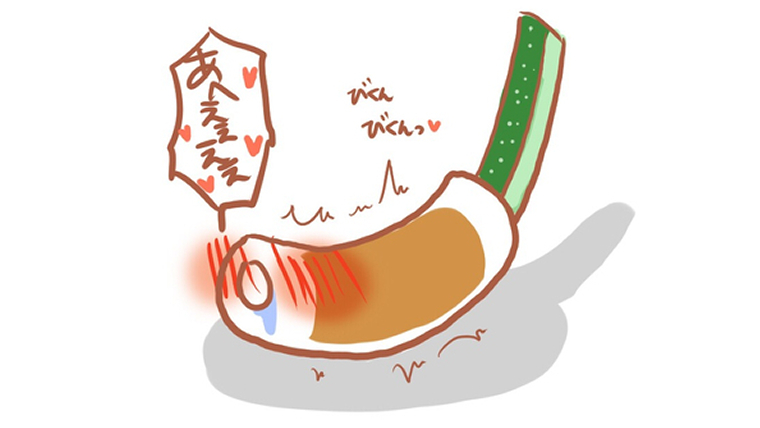【事案】見た目チンピラの元トップアイドルらしきおじさんにしつこく付きまとわれています。
-727x1024.jpg)
アイドル縫ちゃんが芸能界に引き入れられたキッカケ話です。全体的にIQ低めなアホの子紅を、冷静沈着な縫ちゃんがウゼーウゼー言ってるだけの話です。縫ちゃんの毒舌心の声がキレッキレ。もはや半分漫才です。
「……見ぃつけた!!」
雑踏の中で何故かひときわ耳に届く声が、まさか自分に向けられたものだとは、最初は思いもしなかった。
ただ俺はそのデカい声が気になって、一体何だと出所を探った。そしたら目が合った。ソイツと。長身で、赤髪で、サングラスをかけた、お世辞にもお行儀がいいとは言えないタイプの風貌の男だ。そいつが真っ直ぐこちらへ向かってきていた。
え、俺? なんて困惑した時にはもう遅かった。すぐに男は目の前までやってきて、身を屈めて俺の顔を覗き込んできた。
「や~っと見つけたぜ? もう一人の王子様?」
「……どちら様ですか……?」
開口一番わけの分からない事を言うソイツから目を逸らす。やばい、俺今アレなタイプの変質者に絡まれてるかもしれない。
「まぁまぁそう怖がりなさんなって。俺よぉ、これでも芸能事務所の社長でな、今二人組のアイドルユニットの片割れを探してたのよ」
「……はぁ……」
「で、テメェが一際光って見えたから、声掛けた。これって運命じゃね?」
「……」
話が飛び過ぎていて意味が分からない。怖い。
「あの、急いでるんで……」
「まぁまぁまぁまぁちょっとくらいいいじゃねぇの。オニーサンお名前は? 年いくつよ。つかマスク外してくんね? ぜってぇ可愛い顔してんだろ?」
怖い絶対変な人だ。
右へ避けようとすれば相手も右へ、左へ避けようとすれば相手も左へ。逃げようにもガードが固くて通して貰えそうにない。仕方ない、ここは……。
「……あ」
「……あ?」
遠くに何か気になるものを見つけた素振りを見せ、男がそれにつられた瞬間に一目散に人混みの中へと逃げ込む。背後から「あーーーー!」という大声が聞こえたが、知るか!
しかし次の日、男はあろう事か下校時間の校門前に現れた。
「よぉ!」
ただでさえ派手な赤髪なのに、さらに派手な柄シャツを着てゴテゴテにアクセサリーをつけてデカいサングラスをかけているものだから、背の高さも相まって相当目立つ。知り合いだと思われたくない(というか知り合いではない)俺の気持ちなど微塵も考えず、そいつは馴れ馴れしく肩に手を回してきやがった。うっわ煙草くさ。
「勉強お疲れさ~ん♡ 今帰り?」
「何で学校バレてるんですか警察呼びますよ」
「制服で調べたらすぐ分かった♡ いや~いいねぇ中学生。この大人でも子供でもない未成熟な色気……堪んねぇよなぁ~♡ こっから何色にだって染められるもんな~♡ で、今日こそ名前教えてくれる?」
逆に何でその発言の後に名前を教えて貰えると思ったんだ。教えるわけないだろ絶対バカだろコイツ。だんまりを決め込んだまま早足で逃げようとしたけれど、相手は無駄に手足のリーチが長いため何てことない様子で肩を抱いたままついてくる。
「家まで送ってやろうか?」
「結構です」
「も〜可愛くねぇなぁ。子供は大人の好意に甘えるのが一番だぜ? えーっと……朔宮、影縫君?」
「……!?」
教えた覚えのない名前を呼ばれ驚いて顔を上げると、男の手の中には、定期入れに一緒に入れていたはずの学生証が握られていた。
「ちょっとスらせて貰っちゃった〜♡」
愕然とすると同時にあくどい笑顔に腹が立つ。
「返せよっ!」
「うんうんすぐ返すって。つーかさぁ、やっぱりじゃん! やーっぱめちゃめちゃ可愛い顔してんじゃん! こりゃますます諦めるわけにはいかねぇなぁ~」
俺には届かない位置に学生証を掲げた男は証明写真をまじまじと検分しはじめた。ほんと冗談じゃない。こんなの一歩間違えたらもう犯罪だろ。しかも、明らかに教職員でも保護者でもない派手な男に下校途中の生徒達も気づき始め、絡まれている状態の俺も含めて遠巻きに注目を集める形になってしまっている。ああもう最悪だ。人に注目されるの嫌いなのに……!!
そうやって、何とか学生証を取り返そうと躍起になっていると、生徒の一人から悲鳴のような声が上がった。
「ちょっ……ねぇ、あれって一色紅じゃない!?」
それを皮切りにして、他の生徒達にも似たような動揺が広がっていく。
「うおやべっ」
ざわざわと色めき立ち始めたギャラリーを見て、その男は慌てて俺に学生証を押し付けてきた。
「これ、自分で読むかお家の人に見せてくんね?」
それと同時に、資料をまとめたような大判の封筒も。
「また来るぜ♡」
そして俺に耳打ちを一つして、逃げるようにその場を後にした。自動的に、俺は一人で生徒たちの視線の中に取り残される事になる。
(最悪……)
絶対にもう来るな。
知らない男から押し付けられた封筒なんて、薄気味悪すぎて道端のゴミ箱にでも捨ててやろうかと思った。だけどもし今後も付きまとわれて何かしらの事案になった時に、証拠は多い方が警察に突き出しやすい。そんな思いから家に持ち帰り、中身を検める事にした。
あの男が代表だと言い張っている会社だ。一体どんな胡散臭い資料が入っているのか……。と思いきや、内容はといえば会社概要と経営方針、後は「お宅のお子さんをスカウトしたいです」という旨の、どうやら親に向けたらしい書面。しかも全ての文面が驚く程分かりやすくてまともだった。……いや、多分あいつが書いてない。ちゃんとした大人の気配を背後に感じる。
さらに資料には、クリップで一枚の名刺がとめられていた。「株式会社K-product代表取締役社長、一色紅」と。
話が事実だとするならば、これがあの男の事だろう。
(一色、紅、一色、紅……何か聞いたことあるんだよな……)
名刺に記された名前もそうだが、あの男の外見に、派手だというだけでは説明が出来ない、妙にひっかかる部分があった。そして検索エンジンに名前を打ち込んでみた所、謎の既視感の正体が判明した。この紅という男は、数年前に引退を発表して、しばらくテレビを騒がせていたアイドルだったからだ。
芸能情報周辺に興味のない俺の記憶にすら残っているくらいだから、世間一般からすればかなりの時事ネタだったのだろう。特に俺より少し上の世代を中心に絶大な人気を誇っていて、ファンの落胆も相当なものだった……と、当時の日付のネット記事に記されていた。
そして引退後芸能事務所を立ち上げた事も、どうやら嘘ではないらしい。大規模なオーディションで集めた若手の何人かは既にメディアに目をつけられていたり、名前の知れているタレントが移籍したりもしているようで、実業家としての才覚もあったとか何とか。
(……あれが?)
正直にわかには信じがたいが、どうやら何もかもが真実のようだ。
ただ申し訳ないのだが、俺は絶対にアイドルなんてものにはならない。芸能界なんて自分に向いていない最たるものだ。俺はなるべく一歩後ろに下がっていたいし、なるべく裏方をやりたいし、人前で歌ったり踊ったりなんて考えるだけで眩暈がするような性分だ。期待には応えられない。
奴が本当に仕事でやっているのであれば、こちらとしても、明日ハッキリとその気がない事を伝えるのが筋だろう。そんな事を考えながら資料を封筒に戻した。
「すみません。俺、こういうの向いてないし、なる気もないんで、無理です」
今日も下校時待ち伏せしてきた紅に、封筒を突き返しながらキッパリと意思を伝えると、ぽかんと間抜けな顔が返ってきた。しかしその後すぐに不服そうに唇を尖らせ、まるで俺が悪い事でもしたかのような視線を送ってくる。
「何でやりもしないで向いてねぇって分かんだよ」
「いやだって、人前に立つのそもそも苦手だし……」
「いーやそんなわけねぇ! テメェは俺の目に留まったんだぜ? それが向いてねぇはずがねぇ!」
何だその自信。昨日今日顔見知りになった分際で、俺の向き不向きを勝手に決めるな。
「とにかく俺は絶対やりません。迷惑なのでこれっきりにして下さい。これ以上しつこくするなら本当に警察に相談します。それじゃ……」
「ちょーいちょいちょいちょい!! 良くない良くないそういうの良くねぇって!! 最近の若いヤツはそうやってす~ぐ他人と距離取りたがる~! じっくり話さなきゃ分かんねぇ事もあろうぞ~!?」
取り付く島もないレベルで突っぱねたはずだが、紅は一切気にする事無くまたも俺の肩に手を回してきやがった。だからやらないって言ってるだろこいつ耳ついてるか?
「つまり縫ちゃんは恥ずかしがりやさんなんだな? そうなんだろ? 大丈夫大丈夫~。そういうヤツほど舞台に立つとハジけるもんだから~♡ 女の子からの黄色い声援、浴びてみたくな~い~?」
「浴びたくないです」
すげなく断るも、やはり紅は動じずついてくる。
「じゃあもう一回だけでいい!! チラっと見るだけでいい!! 先っちょだけでいいからとりあえず事務所来てみよっ!! な!?」
「知らない人についてくなって言われてるんで」
「こんだけ喋ってりゃ俺らもう友達じゃ~ん!! 縫ちゃんのイケズ~~~!!」
物凄く煩いしヤニ臭い。頼むから耳元でぎゃんぎゃん言わないで欲しい。あと事務所の先っちょって何だ。
「じゃあ~……好きな食べ物! 好きな食べ物くらいならさすがにいいだろ!? ねぇねぇお願ぁ~い♡ お兄さんに教えてぇ~?♡」
突如媚び声を出した紅は、顔の前で手のひらを合わせながら首を傾けた。うっわ……ぜんっぜん可愛くない……むしろキッツ……。このぶりっこおじさんがトップアイドルだったとか、今の世の中どうなってるんだ……。
ただ、いつまでも付きまとわれているこの状況も鬱陶しいし好ましくない。昨日のように他生徒がいつこいつの存在に気付くかも分からない。好きな食べ物くらいなら教えても害はないだろうし、今はとにかくさっさと場を治めよう。俺はそう結論付けた。
「……チョコレートのお菓子……」
「!」
渋々返事をすると紅の瞳が輝く。それから大仰な動作で得意満面に腕を組み、数歩俺から遠ざかっていったので一体何だと思ったら、サングラスを持ち上げながらキメ顔で振り返って人差し指をつきつけてきた。
「また来るから覚悟しとけよ! ぜっっっ……てぇブチ落とす!!」
一々格好つけないと死ぬのかこいつは。
次の日に紅は、真っ赤なバラの花束、しかもドラマでしか見ないような物凄い本数のヤツを抱えて現れた。
「縫ちゃん今日も勉強お疲れさ~ん♡ はいこれ、俺からのプレゼント~♡」
しかも、満面の笑みで差し出してきた花束の中には、某高級チョコレートブランドの箱が埋められていた。物、渡し方、共に明らかに送る相手を間違えている。そのプレゼントを見て俺は冷静に判断した。あ、こいつやっぱりバカだ、と。
花束を受け取る事もなく白けた目線を送る俺と、にこにこと笑う紅との間に、しばし沈黙の時間が流れた。
「……あっれぇ~? なんか刺さってない感じ~?」
その後紅が、場に漂う何とも言えない空気に気付いて首を傾げる。俺は無言のまま頷いた。
「嘘だろオイ! 皆これやるとぜってぇ喜んでくれるぜ!?」
「いやそれ……本気で喜んでるヤツも居るのかもしれないけど、恐らく過半数は気を使って喜んでくれてる……」
「えー!? マジでー!? んな事ねぇと思うけどなー!? だって俺だぜ!? 俺からのプレゼントだぜ!?」
その「だって俺だぜ」って何なんだ。一体どういう生き方したらそんな言葉が口から飛び出すようになるんだ。
「でも……」
謎の自信にドン引きしつつも、バラの花に埋もれたチョコレートの箱を掬い上げる。
「……これは嬉しい。これは貰っとく」
渡し方はともかくとして、チョコレートに罪はない。折角くれると言っているのだから、ありがたく受け取っておこう。
ちらりと様子を伺うと、小刻みに震える紅と目が合った。奴は丸くなっていた目をぎゅっと瞑って、唇も引き結んだ後、花束を思いっきり振り下ろしながら天を仰いだ。バサアッ! 無駄に花びらが散らばった。
「がわ゛い゛い゛がよ゛お゛ッ!! ずっと逃げられてた野良猫が初めて近くに寄ってきてくれた時の気分ってこんななのかなぁ!? なぁなぁこんななのかなぁ!?」
「知らないし、俺を野良猫扱いするな」
動作も声も煩すぎる。突然感情を爆発させないで欲しい。
「あと俺、ポッキーが一番好き」
「安上りで可愛い!! 分かった今度はポッキー山盛り買ってくっからな!!」
「山盛りは持って帰れないから、適量がいい」
「承知しましたマイロード!!」
足を揃えてやたらキレのいい敬礼を披露した紅が、はっとして歯抜けになったバラの花束を持ち上げた。ごそごそと茎を掻き分け始めたので何事かと思ったら、保水処理の水分が染み込んでしなっしなになった謎の紙きれが取り出された。
「なぁなぁ実はサプライズでこの中に契約書も入れといたんだけど~、どうせならこれも持って帰ってくんね~?」
「要らない」
へらへらと馬鹿っぽい笑い方で差し出してくる書類を叩き落とす。「酷ェ!これが指輪と婚姻届けだったら絶対オチる所なのに!」なんて意味不明な事言われたけど、もうコントだろそれ。
そしてさらに翌日、もはや当たり前のように待ち伏せしてくる紅と俺は、学校から少し離れた静かな公園の物陰にひっそりとしゃがみ込んでいた。理由は推して知るべし。うちの学校で「放課後の校門前に一色紅が現れるらしい」という噂が広まってしまったからだ。当然だ。何せ紅はサングラスこそしているものの、それ以外は大した変装もせずほぼプレーンな状態で俺の前に現れるのだ。しかも一々やたらと目立つ言動で絡んで来るのだから、気づくなという方が無理な話だ。
さすがに元一世を風靡したアイドルともなれば、自分がノコノコと一般人の前に現れたらどうなるかくらい承知しているはず。なのに何故一色紅だとバレる恰好で来るのかと問い詰めると、紅はドヤ顔でやれやれと首を横に振ったのだった。
「いや~なんか俺さぁ、どんなに変装してもバレるんだよね~。だからもう好きでもねぇ服着て変装すんのタルくってさぁ~。やっぱオーラってヤツ? 生まれつき持ってる人間はつれぇよなぁ~」
「…………」
うっざ……。
困っているというよりも明らかに自慢話の口調で話す紅にげんなりする。お前がチヤホヤされていい気分になるのは勝手だが、そのせいで迷惑を被っている俺の身にもなれ。
「それより縫ちゃん、はいこれ」
そんな風に心の中で毒を吐いていると、紅が徐にポッキーを三箱渡してきた。普通のヤツと、イチゴのヤツと、アーモンド。
一瞬迷った。これ以上懐柔されていいものだろうかと。上目で様子を伺えば、俺が受け取らないなんて思ってもいないだろう邪気のない笑顔があった。
「……ありがとうゴザイマス……」
「どういたしまして~♡」
結局俺は素直に受け取った。まぁポッキーは嬉しいし。
「じゃ、俺今日ちっと忙しいからもう行くな」
しかし今日もまた鬱陶しい絡まれ方をするかと思いきや、ポッキーを渡すだけ渡してあっさりと立ち上がる紅。そこで気づいたのだが、今日はいつものチンピラじみた服装ではなく、ノーネクタイながら一応スーツを着用している。……ただ社長というより、どちらかといえばホスト寄りなのだが。
「……え? ……これだけのために来たのか……?」
「え? うんそうだけど? だって縫ちゃんのために買ったポッキーだし。今日も可愛い顔見れて嬉しかったぜ♡」
「…………」
「そんじゃまた来るな~気ぃ付けて帰れよ~♡」
そう言うと紅は、ニコニコと笑って手を振りながら去って行った。向かう先にまるで示し合わせたかのように黒塗りの高級車がつけられて、紅が乗り込むとすぐに発進する。
スカウトのために来ているはずなのに、ただポッキーを渡すだけ渡して帰るなんて、目的を見失ってやしないだろうか。
(変なヤツ……)
それからも紅は毎日のように現れて、しつこく俺に絡んできた。
奴はバカの一つ覚えみたいに毎回ポッキーを買って来て、段々と食べきれないそれが溜まっていく。これ以上貰っても仕方ないので、結局別の好きな物を教えるハメになった。といっても食べ物ではなく、今ハマってるスマホゲームだ。そしたら次の日にはアカウントを作ってきて、一緒にやろうぜなんて言い出した。ゲームなんてやらなさそうに見えるので驚いた。聞けばゲーム自体に興味は無いが、縫ちゃんと仲良くなりたいからやるんだぜとサラリと言われた。
頼むから目立つ格好で来るなと口を酸っぱくして言った翌日には、量販店の無地パーカーを着て来たのは新鮮だった。「偉い? 似合う?」って褒められたそうにしてきたから、適当に褒めてやったら翌日からも同じような恰好をしてくるようになった。どうやら扱いやすい部分もあるらしい。ただいくら大人しい格好をさせた所で何故か一目で紅だと分かるので、以前の自慢話に合点がいった。
煙草を吸ってみるかと聞かれたから、興味本位で吸ってみた。マズい以前にむせてまともに吸えなかった。そんな俺を見てげらげら笑う紅が、深々と肺まで煙を流し込む様子が信じられなかった。でも悪友が出来たようで、ほんの少しだけ楽しかった。
それだけ付きまとわれればさすがに紅という存在に興味も湧いてくる。検索をかけて上位に出てきたミュージックビデオを再生してみると、いつものアイツが画面の中で笑ってしまうくらいに恰好をつけていた。普段から動きが煩いので踊りは得意そうだなと思っていたが、あれだけヤニを吸っておきながらやたら歌が上手い事には感心した。余計な事をせずに画面内で祭り上げられてさえいれば、確かにあの派手さも人目を惹き付けるアドバンテージとなっている。コイツ本当にアイドルだったんだなと、今更ながら認識を改めた。
ただ……俺自身がこれをやりたいかと聞かれれば、やっぱり全然やりたくなかった。
「昨日あんたのMV見た」
話を切り出したのは車の後部座席。校門の前は勿論の事、あの静かな公園も、コンビニ近くの路地裏も、何故か人が集まるようになったので、最終的にはスモークガラスの車の中が俺達の定位置となった。今日のオトモは紅が買ってきた……正確には、紅の運転手が買ってきたコンビニのコロッケだ。隣でメンチカツにかぶりついていた紅が、その一言でぱっと目を輝かせた。
「マジでー!? 俺のヤツ見てくれた!? 嬉しいぜ~♡ なぁなぁ、俺かっこよかっただろ~?」
「普通」
「ったく縫ちゃんってば素直じゃねぇなぁ~。で、それ見て自分もやりたくなったりとか~?」
「絶対やりたくないって気持ちが強くなった」
「あっはっはっはっは!! 裏目~~~~!!」
紅は膝を叩きながら爆笑している。何がそんなに面白いんだろう。今日もスカウトを蹴られてるわけなのに。
「……なぁ、あんた……」
「?」
「無駄だって思わないのか? 見込みのなさそうな相手に時間使って」
しかし紅はといえば、その問いにきょとんと首を傾げるのみだった。
「何で?」
「何でって……俺がこの先も結局やりたいって言わなかったら、時間が全部無駄になるだろ」
「……え? だから何で? 無駄じゃなくね?」
「は? だから……」
俺は理にかなった事を言っているはずなのに、何故か話が通じない。本気で困惑している様子の紅に対してさらに言葉を継ごうとした所、先に向こうに口を開かれた。
「だって俺は縫ちゃんと一緒に居るの楽しいぜ?」
思ってもいない返しに、今度は俺が呆けさせられる番だ。
「まぁそりゃ最終的に事務所来てくれれば何よりだけど~♡ それはそれとして、今こうしてんのも楽しいじゃん」
「…………」
「じゃあ仮に縫ちゃんが事務所来なくても、楽しかった時間が残るから無駄じゃねぇじゃん?」
「…………」
「分かる?」
無駄に真っ直ぐな瞳でこっぱずかしい事を言われ、さすがに胃の辺りが浮いた感覚がした。それこそ自分は「一緒に居て楽しい」と思われるタイプでない事は理解しているつもりだ。だから余計に。
「……楽しくないだろ。俺なんかと居たって」
「あはっ♡ そのセリフ、『そんな事ないよ♡』って言われたがってる面倒くせぇ女みてーで可愛い~♡」
頭を抱え込んでペットみたいに撫でまわしてくる紅がウザくて、やめろって無理矢理引っぺがした。一切申し訳ないとは思っていなさそうな笑い声が返ってきた。
「縫ちゃんは優しいなぁ」
「は? 優しくないけど」
「だって今の話、つまり俺が損被らないように気にしてくれてるって事だろ~? やべー惚れちゃう~♡ 末恐ろしい子~♡」
俺が半分も食べない間にメンチカツを平らげた紅が煙草を咥えた。ちらりと俺に目くばせして、今日も吸う練習をしてみるかとジェスチャーする。コイツが口をつけた後の煙草を咥える趣味はないので、丁重にお断りした。
「ま、気にしなさんな。テメェがウチ来ようが来なかろうが、逆恨みなんざ野暮な事はしねーからよ」
シュッ。龍の目を象ったジッポが着火し、煙草の先端に火が灯る。
「例えばさぁ、女口説いてオチなかったからって文句言う程無粋な事ってある? ねぇよなぁ。それと同じよ」
あいにく俺にその実体験はないが、言いたい事は感覚的に理解できた。
「俺が好きで口説いてんの。縫ちゃんの事口説きたいから、俺の意思で口説いてんの。テメェの意思でやった事の結果がどう転んでも、んなモンテメェでケツ持つっつーの」
いつものふざけた調子を剥がし取った言葉達が、心地よく耳に滑り込んでくる。
「……女口説く時間を楽しめるから、俺はトップアイドルだったんだよ」
紫煙の向こうで瞼が伏せられた。とんだ気障なセリフだが、第一線に立ち続けたコイツが言うなら、あながち間違いでもないのだろう。
紅という人間の内側が、ほんの少しだけ分かった気がした。
だけどその日を境に、紅はぱったりと姿を見せなくなった。
校門を出て辺りを見回す。友人と下校する生徒、外周を走り込みする運動部、送迎に来ている保護者の車。ごく一般的な放課後の風景が広がっている。通学路にある静かな公園にも、コンビニから一本入った路地裏にも、今日もどこにも、あの赤髪の姿は無かった。
(……まぁ、それはそうか)
脈の無さそうな相手をスカウトし続ける程バカげた話もない。俺の話を聞いてこれ以上は時間の無駄だと判断し、すっぱり見切りをつけたのだろう。煩いヤツが居なくなってせいせいした。もうしつこく付きまとわれる事もない。
(聞こえの良い事言ってたクセにな)
それなのに、何故俺はどこか失望にも似た感情を抱いているんだろう。もう来るなと思っていたのに。鬱陶しいと思っていたのに。あいつに何か期待していたとでも言うんだろうか。
馬鹿馬鹿しい。所詮他人だ。先生でも友人でも、まして家族ですらない。
赤の他人だ。
実は芸能関係のスカウトにあったのは紅が初めてじゃない。今まで何度もこういう事があった。それが嫌で、面倒で、もう声をかけられたくなくて、マスクで顔を隠すようになった。
そもそも小さい頃からそういうのに声をかけられやすい性質だった。そういうの、というのは、れっきとした芸能事務所のスカウトのようなマトモな物ばかりじゃない。ただの不審者もいれば、未成年を食い物にしたがる大人も居る。厄介なテアイには毅然とデカい声の一つでも上げられればいいのだろうが、生憎俺は生まれつきそういう風に振る舞えるタイプではない。大事に至った事はないが、嫌な思いをした経験は人並み以上に多い。そんな経験を繰り返すうち、声をかけてくる大人達の裏側に張り付いている「何か」を勘繰るようになってしまった。
だからこそ、紅の言動が本当に裏表のない純粋なものなんじゃないかと、掛け値なしのものなんじゃないかと、そう思いたかったのかもしれない。
ただそんなものは俺のエゴだ。紅には関係ないし、ヤツには何の落ち度もない。仕事は仕事だ。別に俺達は友人なんかじゃない。俺もアイドルになるつもりはない。だったらそれまでだ。
嵐のように現れて、ズケズケと人の心に入り込んで、俺の日常を掻き乱して、そしてまるで最初から存在しなかったように、ぱったりと消えた。
もしかするとアイツ、夢か幻だったのかもな。そんな非現実的な事を思いながら、静かな帰り道を歩いた。
だけど心に隙間がある時は、妙なヤツに付け込まれやすいらしい。
「ねぇねぇ君可愛いね~! いいアルバイトの話があるんだけど興味な~い?」
モヤモヤした気分のまま大通りの方まで出たら、ガラの悪い男三人組に捕まった。一人は脱色した金髪、一人はスキンヘッド、一人はオールバックで、カタギっぽいとも、品が良いとも言い難い見た目だった。
「大人の人と一緒にご飯食べたり遊んだりするだけでお小遣い稼げるんだけどさぁ、学生さんってお小遣い足りないでしょ?」
「えと……そういうのは、ちょっと……」
「あっもしかしてヘンな想像してる? 大丈夫大丈夫! お茶飲みながらお話するだけだから! それに綺麗なお姉さんもいっぱい利用してるお店だし、お姉さんとデートして好きなもの買って貰ってお金貰えるとか最高じゃない?」
「誰でも出来るわけじゃなくて、君みたく若くて可愛い子だけに特別に声かけてるバイトなんだよね~。折角だからやっとかないと損だよ~?」
一人の手首を掴まれた。思った以上に力が強くて、まるで逃がさないぞって言われてるみたいで、サッと背筋にうそ寒いものが走る。
「ね、ね、とりあえずこの近くに事務所あるからさ、そこでゆっくり話だけでも聞いてみない?」
「あ、あの! ほんとに結構ですっ……!!」
身の危険を感じて振り切ろうとするも、男はそれ以上の力で引っ張ってくる。最悪だ。目立たないようにしてるのに、何でよりによってこんなのに目を付けられるんだろう。やだ、怖い、どうしよう。誰か、助けて……!
と、そう願ってぎゅっと目を瞑った瞬間、煙草の匂いと共に肩へ腕が回ってきた。
「はいはいは〜い、俺のカワイイ弟に何の御用ですかぁ〜?」
聞き覚えのある声に顔を上げる。そこに立っていたのは、ここ最近姿を見せなかった紅だった。
金縁のサングラスをかけ、派手な柄物シャツの襟ぐりからごついアクセサリーを覗かせ、咥えタバコのその風体は、目の前の奴らと比べてもどっちが輩なのか分からないくらい、ガラが悪かった。
「な……何だテメェ……」
実際男達は明らかにたじろいでいた。気持ちは分かる。それはそう。
「あ? だから今言ったろ。コイツの兄貴だよ兄貴」
メリケンサック並に指輪のハマった指で煙草をつまみながら、悪びれもせず嘘を吐く紅。
「いや嘘つけよ! 見た目がどうとか言うレベルの問題じゃねぇぞ!? なんかこう……とにかく何もかもが似ても似つかねぇだろうが!!」
「こんな清楚で可愛い子とテメェとの血の繋がりがあって堪るか!!」
「何言ってんだこの節穴共が!! 似てるだろ!! めちゃめちゃ美形の遺伝子って所が瓜二つだろ!!」
「おいこの野郎自分で言ったぞ!?」
「ぐっ……しかし何だこのオーラは!? こいつ確かにタダモンじゃねぇぞ!?」
こればっかりは流石としか言いようがないが、紅が乱入してきた瞬間場の空気がヤツに飲み込まれた。強すぎる圧に負けてじりじりと後ずさりする男達。その中の一人がはっと我に返ってかぶりを振る。
「お、おい騙されてんじゃねぇ! ただ派手な恰好してるだけだろうが!! おいアンタさては同業だろ!! 悪ぃがこの子はうちが先に目ぇつけたんだよ!! 今更横取りしようなんてふてえ野郎だ痛い目見ても知らねぇぞ!!」
「はぁ~~~~? 同業ってなんの話ですかぁ~? 怖ぁ~い! 俺は健全な一般ピーポーなんでぇ、こんなガラの悪いあんちゃん達がやってる事業が何なのかなんて皆目見当もつきませぇ~ん! つか俺マジでこいつの兄貴なんでぇ、難癖つけんの止めて貰えます~? ぶっ飛ばしますよ~?」
男達が拳を鳴らして凄んでも、紅は全く怯む様子を見せない。声のデカすぎる輩同士の言い争いはさすがに目立つらしく、通行人達も遠巻きながらチラチラとこちらを伺う様子を見せ始めた。このままではまたいつコイツが「一色紅」だと気づかれ騒ぎになるかも分からない状況だ。
「な、縫ちゃん? 俺ら兄弟だもんなー?」
そんな中、紅が見計らったようなタイミングで俺に話を振ってきた。この事態を脱するためにどういう行動をすべきか。答えは一つしかないだろう。
「……う、うん……お兄ちゃん……」
痒さと鳥肌を必死に我慢しながら、紅の服をきゅっと握って頷いた。見なくても分かる。こいつ絶対死ぬ程ドヤ顔してる。
「はぁ~いそういうコト~~~♡ 本人から言質取ったのにアンタらがこれ以上ピーピー騒いでいい理由はねぇよなぁ? これ以上弟に付きまとうなら警察呼びますよ~? おたくらおまわりさんに説明出来るような清い商売してる~?」
先程よりもさらに傲慢ちきな声になった紅がスマートフォンを取り出すと、さすがに男達も分が悪いと判断したらしい。ちらちらと目くばせをしあった後、リーダー格らしい男が舌打ちを一つ。
「覚えてろよ!」
「負け犬の遠吠えご苦労さ~ん♡ おととい来やがれ三下がよぉ!!」
お決まりの捨て台詞に対して、げらげらと笑う紅が中指を立てて煽り返す。それ以上は何を言うわけでもなく、男達の背中が遠ざかって行った。
「いやぁ~嘆かわしいねぇああいうテアイは」
「いやお前も俺に対してほぼ同じような事してるからな」
「いやいや俺のはやましい事業じゃねぇもん。ロードーキジュンホーにのっとった運営してっから。うちの会社クリーンなんで~♡」
ああ言えばこう言うで返した紅が、サングラスを持ち上げ俺の顔を覗き込んだ。人懐っこくて真っ直ぐな瞳。海みたいな色だと思った。服装や素行は似たり寄ったりだが、今しがたまでの男達とはやはり何かが違った。
「最近ちぃーっとばかし忙しくてよぉ、遊びに来れなくてごめんな~♡ 寂しかった? ねぇねぇ俺に会えなくて寂しかった~?」
「うっっっざ……」
別に寂しくなんてなかったけど、急に顔を見せなくなった事を少しだけ気にしていた自分の気持ちを気取られるのが癪で、わざと顔を歪めて毒を吐いた。紅が来てくれてちょっとホッとしたとか、まして嬉しかったなんて、思っていない。
だけどいつもは何を言われてもヘラヘラしているはずの紅が、俺の反応を受けて眉尻を下げ、唇を尖らせ、みるみる悲し気な表情になっていった。これにはさすがにぎょっとした。
「俺……ホントはすっごく怖かったんだぜ!? でも縫ちゃんが困ってるから、何とかしてやらねぇとって思って……!! 可愛い可愛い縫ちゃんのために勇気振り絞ったってのに、それでも尚邪険にされるなんて……ッ……あぁ何て可哀想な俺!!」
そこまで言うと、紅は大袈裟な動作で顔を覆って項垂れた。ぐずぐずとわざとらしく鼻をすする音が聞こえてくる。いや……水を得た魚みたいにノリノリで口喧嘩しといて何言ってるんだ。嘘くさすぎて逆にリアクションに困るんだけど……。
ただ紅が来てくれなければ対処しきれなかったかもしれないのは認める。悔しいが、助けられたという事実に違いはない。
「いや、その……感謝はしてるけど……」
「……じゃあうちの事務所来てくれる?」
恩を売り、俺が断りづらい土台を作った上で、いかにも可哀想ぶりながら、自分の要望を捩じ込んでくる。
……下手したらさっきのヤツらよりタチが悪くないかこれ。
「わ……分かった……一回だけ、見学くらいなら……」
「えっ、マジでー!? じゃあ気が変わらないうちに行こうぜ~♡」
言うや否や、紅はケロリとした様子で顔を上げ、意気揚々と俺の腕を引いて歩き出した。
うん……泣いてないのなんて分かり切ってたから、何も驚かなかった。
事務所へ連れていかれる車の中で、今更ながらとある疑問が浮かんだ。
「……お前の会社、所属タレント結構居るんだろ? 何でその中から見繕わなかったんだ?」
そう。何故わざわざここまでの熱量で俺に声をかけて来たのだろうという事だ。確かネット記事にも、オーディションまでして若手を集めたと書いてあったはず。俺が乗り気ならともかくとして、ここまで嫌だやらないと突っぱねられれば、普通ならじゃあ所属タレントから選ぼうという考えになるのではないだろうか。
「ん? まー……ピンと来なかった? ユキの隣に並べるのが」
「……ユキ?」
「俺最初に『二人組のアイドルユニット』って言ったの覚えてる? その片一方で、俺お墨付きの可愛こちゃん♡ 今日も居ると思うからよ、後で紹介すんな」
「……はぁ……」
情報が少なすぎてリアクションがしづらいが、どうやら先輩という事らしい。そうか……俺、今からアイドル候補生と話すのか……。華やかで煌びやかな世界とはどうも相性が良くないため、早速少し気が重くなった。だがそんな俺の心境など気にする事無く紅が話を続ける。
「まー何せうちのタレントは俺が選んだヤツらだし? 誰並べてもそれなりに様にはなんのよ。ただど~も何かがハマんねぇ。映像が浮かんでこねぇ。そんな状態で妥協した所で妥協したなりの結果が出るだけだ。それでモヤモヤしてる時にぱっと目に飛び込んできたのが、縫ちゃんよ」
そこまで言うと紅は突如シートを引っ叩き、拳を握って俺の方へと身を乗り出してきた。さすがに驚いて肩が飛び跳ねた。
「ぜってぇ、ぜーってぇコイツだって思った。あの瞬間、歩いてる縫ちゃんを見かけた瞬間に、こう、ブワーーーって目の前に広がったのよ。ホールを埋め尽くす大観衆、キラッキラ光るサイリウム、その中心でスポットライトに照らされる陰と陽が!! これだよこれ!! 俺が求めてんのはこれだーーー!! って魂が震えたね! 俺の目に狂いはねぇ。俺が鳥肌立つくらいに感じた事は真実だ! だから俺には、テメェらという存在を全世界に知らしめる義務がある!!」
頬を高揚させ、目をキラキラさせながら、身振り手振りと共に早口でまくし立てる様子は、まるで規格外の夢を語る子供のようだった。今まで見たどんな表情よりも楽しそうで、馬鹿馬鹿しいくらい真っ直ぐなエネルギーが伝わってきてビリビリする。それを聞いていると、億劫さに囚われていたこっちまでついうっかり楽しい気分になってしまいそうで、俺は平静を取り繕うため慌ててマスクを引き上げた。この時初めて垣間見た。こいつの、民衆を熱狂させ続けた偶像たる片鱗を。
「……言っとくけど、あくまで見学するだけだからな」
「あっ、もうそういう事言っちゃう~? いいぜ♡ 明日も明後日もその次も、い~~~っくらでも! 気の済むまで見学していきな♡」
ちゃっかりこの先も俺が事務所に行く事にしてくる都合の良さに、今度こそ笑いが零れた。
こちらもおすすめ