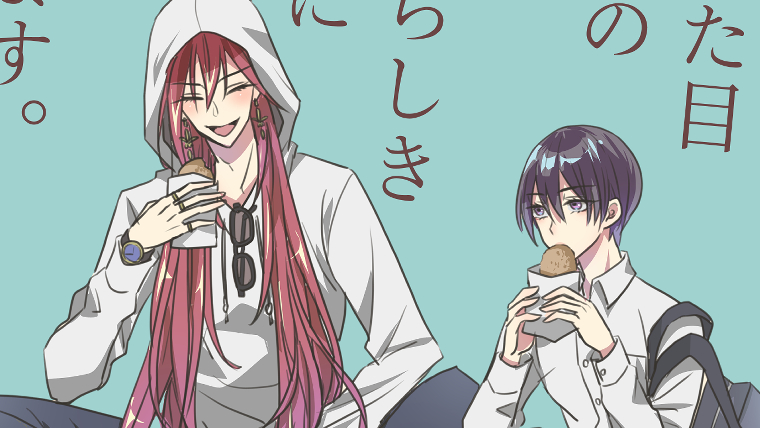もっと触って、大好きだから。

一色空と桃瀬妃は、アイドルグループのメンバー同士であり、お付き合いをしている仲でもある。
優しい恋人にお姫様のように大切に扱われる満ち足りた日々。だがその一方で、妃は空が性的な触れあいをして来ない事を密かに思い悩んでいた…。
二人の距離
芸能事務所Kプロダクトに所属する「ライトハウス」は、男女混合四名構成のアイドルグループだ。
メンバーは全員子供の頃から付き合いがあり、大人になってから組み合わさったグループとはまた違う仲の良さが持ち味。昔から応援しているファンの中には、保護者のように成長を見守っている者も少なくない。
一色空(いっしきそら)は、そんなライトハウスを構成するメンバーの一人である。ライオンのたてがみのような癖のある青い髪の青年で、顔体つきのどちらもあと一歩だけ大人になり切れていない未成熟さを残している。誕生月も考えるとメンバー最年少なので、可愛がられる役回りになる事が多い。
彼は新曲レコーディングに向けてのメンバー全体練習を終え、帰り支度をしている最中であった。大学の講義に使うタブレットや教科書と、新曲の楽譜が混ざったカバンの中身を確認し、ファスナーを閉じる。
「空君」
そこで空に声をかけたのは、ゆるくウエーブする桜色のロングヘアが印象的な美女だ。整った顔立ちながら気取った雰囲気はなく、表情や仕草はむしろ可愛らしくて親しみやすい印象がある。
彼女は桃瀬妃(ももせきさき)。空とはライトハウスのメンバー同士だ。
「妃ちゃん、お疲れ様~」
「お疲れ様。あのね……今日この後って、何か予定あるかな?」
愛想よく挨拶をする空に対し、妃が顎を引きつつ控えめに問いかけた。すると空はレッスン終わりの気の抜けた表情から一転。彼女の言いたい事を理解したらしく、すぐさま首を横に振った。
「ううん大丈夫! 大学の課題も無いし、時間ある! 妃ちゃんは……」
「良かった。私も何も無いんだ。だから、良かったら」
「じゃあ一緒にご飯食べに行こう!」
妃の言葉を先取りする形で、空が食い気味に提案する。どうやら妃も同じ思いで声をかけていたらしく、空の言葉を受けてほんのり頬を染めながら頷いた。
「ちょっとちょっと~、二人だけで何の相談~? ボクも一緒に連れってってよ~!」
そんな、どこか甘酸っぱい空気の二人に割り込む悪戯っぽい声。その主は、オレンジ髪を高い位置でツインテールにした小柄な女性だ。体の厚みがなく童顔で幼い印象を受けるが、その実メンバーで一番年上の星野明歌音(ほしのあかね)である。グループ内どころか事務所全体で見ても歌唱力が突出しており、男女問わず多くのファンがついている。
「だっ、だめ! 今日は妃ちゃんと二人で行くの!!」
「えー? 何で何で? 皆で行った方が楽しいじゃん」
ムキになって拒否する空に見せつけるような形で、明歌音がにまにまと笑いながら妃と体を密着させた。憎めない仕草に妃は苦笑を返すのみだが、空は焦った様子で二人を引きはがそうとする。
「ちょっとやめろよ! 触り方がやらしい!」
「いいじゃん女の子同士なんだからさ~!」
「明歌音の場合は絶妙に意味が変わってくるの!」
「やだー! ボクも一緒に連れてってくれるまでやめな~い!」
ちなみに彼女、何を隠そう恋愛対象が女性のガチレズなのだ。
「明歌音やめときなって。二人が困ってるでしょ」
と、困ったちゃんムーブをかます明歌音を窘める声が。帰り支度も済ませ、すでに扉の前に立つ細身で金髪の青年からだ。彼は城崎(しろさき)ルークといい、端正な顔立ちで圧倒的ビジュアル担当。さらに言うと皆を纏めるリーダーでもある。
「またまた~! るー君だって皆でご飯行きたいでしょ~?」
「僕はいい。こんな時間に外食すると肌に悪いから」
ルークを味方に引き込もうとするも一刀両断されてしまい、面白くなさそうに頬を膨らませる明歌音。そんな彼女に嘆息しつつ、ルークは空と妃に視線を移した。
「……ま、メンバー同士でご飯はいいけど、人目がある場所でそういう雰囲気だけは出さないでよね。このご時世、一般人でも簡単に拡散できるんだから」
含みを持たせた一言を残し、「じゃ、お疲れ」と部屋を出ていくルーク。リーダーに釘を刺された空と妃は、すでに本人が居ないにも関わらず肝に銘じますとばかりに頷いて、明歌音は唇を尖らせながらルークが出て行った扉を睨みつけている。
「あーあ、るー君ってばクソ真面目でつまんなーい! じゃあボクも帰ろっかなー。後は若い二人でごゆっくり〜」
だがどうやら、明歌音も本気で邪魔がしたかったわけではないらしい。彼女はぱっと空気を切り替えて、カバンを担ぎ、愛嬌のある笑顔と共に部屋を後にした。
一色空と桃瀬妃は、グループで活動を共にするメンバーであり、そして恋人同士でもある。
同い年の二人の出会いは、互いがKプロダクト事務所入りした小学生の頃。同期として共に歩む中で自然と惹かれ合い、それなりに長い期間の両片思いを経て、最近になってようやく想いを伝えあった所だった。ちなみに他二人のメンバーも、空と妃の関係については認知している。
二人が向かったのは、事務所の先輩にお勧めされていた個室席もある洋食店。少し遅い夕食を取りながら、互いの大学生活や、今日の仕事の反省会、あとは明歌音の面倒ながら憎めない言動と、ルークの美容への生真面目具合など、日常をネタにひとしきり笑い合った。かといってずっと喋り続けているわけではないのだが、その沈黙すらも気まずくなる事はない
最後に二人でデザートを注文し、出てきたのはクマの顔を模した可愛らしいケーキ。思いがけずテンションが上がってしまい、二人でメロメロになりながら写真を撮った。空と妃は昔から、どこか似ていて波長が合うのだ。
「美味しかった~」
ラストオーダーのお声がかかったタイミングで店を出て、二人で歩く帰り道。メンバー四人のグループチャットに、先ほどのクマケーキの写真を送信した妃がほくほくとした笑顔を見せた。その表情を横から眺め、空の口元もほころぶ。
「明歌音ちゃん、すぐ返信来たよ。ずるい~って」
「今度は皆で行きたいね」
「るー君はもう寝てるかな」
「あの人ほんと早く寝ろ寝ろ煩いからな~」
「ふふっ。ちょっとお母さんみたいだよね」
季節は冬へと向かっていて、朝晩は冷え込みが厳しくなってきた。賑わいのある通りから離れ、閑散とした路地に入った所で妃の指先が控えめに空の手の甲に触れた。ちらりと周囲を確認した空が、応えるように手のひらを結ぶ。くすぐったそうに視線を交わして、体温を分け合いながらゆっくりと歩を進める。
二人のグループは、残念ながら「大人気アイドル」と呼べるまでの知名度はない。だけど活動を続ける中で年々ファンを増やしてきて、持ち味を生かしたとあるSNS動画がバズったりもして、今では大きなハコも埋められるようになってきた。
最近はありがたい事に顔をさされる機会も増えてきて、さすがに人目がある所で手を繋いでは歩けない。無論この関係が続いていけば、どこかで公表するタイミングは訪れるだろうが、それは少なくとも今ではない。
だから仕事終わりの暗くて静かな帰り道は、二人にとって、何気ない普通の恋人らしさを楽しめる貴重な時間だった。
程なくして、二人は妃の自宅マンション前に到着した。
「じゃあ……今日も楽しかった」
名残惜し気な空の声と共に結んでいた手が離れ、温め合っていた部分を冷気がなぶる。
「あ……うん。方向違うのに、いつも送ってくれてありがとう」
「そんなの当然だよ。気にしないで」
「えっと、空君も、帰り気を付けてね。もう遅いし……」
「あはは、子供じゃないんだから大丈夫だって」
内容なんてほとんど無い雑談が、二人をその場に引き留める。さっきまでの食事が美味しかった事を反芻したり、分かり切っている明日のスケジュールを意味もなく確認したりして、どちらからも終わりが切り出せない。するとまどろっこしい空気に横やりを入れるように、北風が二人の間を通り過ぎて行った。突然の肌寒さに、思わず妃が肩をすくめる。
「あっ、ごめん寒いよね! 俺もう行くから、入って入って!」
妃の仕草を見て気をきかせた空が、手振りを交えながら帰宅を促した。妃は頷き返し、同意する素振りを見せたのだが……。結局何かを思案するようにその場に留まって動かない。
「……妃ちゃん?」
もう一度空が声をかけたタイミングで、意を決したように。妃が空の袖口をつまんだ。
「ね、ねぇ空君……ちょっとだけ、うち、上がっていかない……?」
上目遣いでの提案は、頬が真っ赤に染まっていて、言葉尻が少し震えていた。
ぐっと、空が一瞬心揺らいだ様子を見せる。彼はむずむず動いた口元を手のひらで覆い隠しながら目線を外し、困ったように笑って……そしてその後、優しく妃の体を抱き寄せた。背中に回した手に、柔らかく力が籠められる。
「……こんな時間に、おうちには上がれないよ」
妃の顔の隣で声がする。その声は切なくて、申し訳なさそうで、今空はどんな顔をしているのか不安になった。付き合ってるんだからそんな事気にしなくてもいいのに。もっと一緒に居たいよ。なんて言葉が妃の喉の入り口まで出かかって、だけどあと一歩の所で音にならなくて、それは胃の方まで落ちていってしまった。
「そ……そう、だよね。明日もあるし……変な事言ってごめん」
結局口からは、聞き分けのいい言葉しか出てこなかった。
そっと温もりが離れていく。改めて見た空の顔は、少し情けなく眉尻が下がった笑顔だった。頬が薄っすらと朱を帯びている。きっと寒さからではない。
「ううん。俺の方こそごめん。いきなりハグしちゃって」
そんなの全く問題じゃない。だって、本当は、もっと……。なんて、妃は頭の片隅で考えて、でももはや言葉になんて出来るはずもなくて「大丈夫だよ」なんて、当たり障りのない返事をした。
「それじゃあ、また明日ね」
「うん、おやすみ妃ちゃん」
「……おやすみ、空君」
寂しさを抱えながら踵を返し、マンションに入っていく妃。静かなエントランスに響く自分だけのヒールの足音が、なんだか無機質で物悲しく感じてしまう。
エレベーターに乗る直前に後ろを振り返ると、まだ入り口前で見送ってくれていた空が手を振って笑った。妃もそれに応えるように控えめに手を振り返して、そして今度こそ、自分の部屋へと帰っていった。