それでも生きていく Ver.月影

2019年11月にpixivに投稿したものです。今回の主役は月影さん。弱くて、未熟で、愛おしい。沢山の人に愛されて、助けられて、今がある。そんな彼の足跡のお話です。こちらもどうぞ それでも生きていくVer.武蔵
響き渡るブレーキ音。
ざわめく人の波。どこからか沸き起こる甲高い悲鳴。
コントロールを失った鉄の塊が、勢いよく、自らの脇を掠めていく。
目の前で人形のように放り出される華奢な肢体。飛び散る赤と、体の内側。
『ッ―――!!!』
引き攣った声で叫ばれた名前は、もう、彼女には届かない。
「華菜さんッ!!!」
金切声を上げながら飛び起きると、そこは真っ暗な部屋の中だった。
普段よりも早いペースで脈拍する心臓。浅く乱れた呼吸音。次いでカチカチと規則的な秒針の音を認識し、徐々に、目が慣れていく。そこまで感じて、ようやっと、何が起きたか理解した。
(ああ)
じっとりと湿り気を帯びた頬から耳にかけてを手でなぞり、自分が泣いていたのだという事を悟る。
(またあの夢だ)
ここは、自分の部屋のベッドの上。
「あの時」の事を、夢に見ただけ。ただそれだけだ。
そう、理解した。頭では理解した。だが、体が思考に追いつかない。手はカタカタと震え、心臓が早鐘を打ち、呼吸は浅く早いまま。涙は、何時まで経っても止まらない。脳の裏側にべったりと張り付いた、愛しい人がこの世から居なくなったその瞬間が、悪夢という形で、何度も、何度も、目の前に現れる。
軽い過呼吸の状態に陥った月影が、ベッドから下りて部屋を出た。せわしなく呼吸を重ねながら廊下を歩き、向かったのは子供部屋だ。
ドアノブに手を掛けて、出来る限り静かに扉を開く。そしてベッドの中、布団から覗くまあるく黒い頭を見た瞬間、足元から力が抜けて落ちる程に安堵した。
良かった。
生きている。と。
ふらふらとベッドサイドにしゃがみこみ、シーツに顔を突っ伏して蹲る。「かげぬい」音になるかならないかの声で、縋り付くように息子の名前を呼んだ。頭を持ち上げると、規則的に上下する掛け布団と、こちらに背を向けた黒髪がぱらりと枕に散らばっている様子が目に映る。その事実を確認して、おおきく、ゆっくりと息を吐いた。
「生きてる……」
頭の中に浮かんだ言葉を、自分に言い聞かせるように、吐き出した。
それでも生きていく
「おぅい、月影ェ~~~!」
会社の廊下を歩いていると、背後から声を掛けられた。大きく手を振りながら駆け寄ってくるのは、会社の代表であり、ビジネスパートナーの理人だった。
そして、大人になってからの付き合いではあるのだが、あまり人との深い関りを持ちたがらない月影にとっては珍しく、本音も晒す事の出来る気の置けない友人でもあった。
経営者として必要な、クレバーで、打算的で、戦略家な気質を持っているが、それと同じだけ、人への情の深さや、素直さ、裏表のない優しさを持ち合わせている人間でもある。
「今度合コン行かね? 合コン! 写真見せてもらったけど、めーっちゃ可愛い子ばっかなの! しかもなんと! 全員ナースちゃん! なぁなぁ、お前も来いよ~! 来るだろ? なっ?」
軽い調子で誘いつつ、月影の肩に腕を引っかける理人。子供のようなうきうきとした笑い顔が、斜め下から覗き込んでくる。その瞳の奥に、深い優しさと心配を垣間見て、月影は咄嗟にそれから目線を外した。あまりに心苦しかったからだ。
「……すみません」
そして、ぽつりと謝罪の言葉を口にした。
理人の表情が、一瞬切なげなものを滲ませて、それからやりづらそうに、ゆっくりと微苦笑の形に変わる。
「……そ、か」
ゆっくりと、肩から腕が滑り落ちた。
「あーあ。お前が来ると女の子の食いつき違うのにな~」
しかし、一瞬流れたなんとも言えない空気も、理人がすぐさま声色を変える事で拭い去られる。唇を尖らせながらの自分勝手な言葉に、月影は思わずぷっと吹き出した。
「何ですかそれ。私をダシに使わないで下さい」
「それのな~にが不満だよ! どーせ何もしなくてもモテんだから、大人しくダシくらいやっとけっての!」
「ふふっ」
理人は華菜が亡くなって以降、度々こうやって、新しいパートナーを見つけさせようと提案してくれる。しかしその度に月影は、首を横に振っていた。
誰かが聞いたら、故人に依存していると言うだろうか。過去にいつまでも捕らわれるなと言うだろうか。現実を見ろと言うだろうか。
でも、それでも、あの人以外の人間が自分の隣に居るなんて、もう考えられなかった。ましてそれが、自分の上澄みだけを眺めてしなっぽく言い寄ってくる相手ならなおさらだ。私はお料理が得意です。すごい仕事についてます。おしゃれにはこだわりがあって、常に可愛くいられるように意識してる。それに友達が沢山いて充実した毎日を送っているの。どうどう? 魅力的でしょ?
そんな風に、まるで履歴書を見せるかのようにアピールしてくる女性達を、自分は限りなく冷めた目線で俯瞰して眺めている。何の情も湧かない。好きだとも、嫌いだとも、思えない。
どうでもいい。それが、一番適切な表現だった。
『ドタ参でもいいから気が向いたら来いよ!』
ホテルのラウンジで人を待っている最中に、スマートフォンがそんなメッセージの受信を知らせた。添付ファイルもあったので見てみると、数人の女性と共に撮られた理人の写真が添えられていた。
ああ、そうか。この間誘われた合コン、今日だったんだな。
(楽しそうな顔)
破顔する友人の表情を眺めていると、自然と口元が綻んだ。理人には、そこに居るだけで否応なしに周囲を明るくさせてしまうような不思議な素質が備わっている。月影自身には絶対に持ち得ないソレが、鬱陶しい時もあるのだが、反面羨ましくあったりもした。まぁ、こんな事を言おうものなら調子に乗るのは火を見るより明らかなので、絶対に言ってなどやらないが。
「こんばんは」
どんな返事を返すのが適当か、思案しながら指を彷徨わせていると、意識の外から声が掛けられた。はっとして顔を上げると、待ち合わせていた男その人が立っていた。月影の表情が、すぐさま余所行きの笑みの形を取り繕う。
「こんばんは」
「待たせたかな? 誰かから連絡?」
「あ……はい。友人からメールが。でも大した要件ではないので、大丈夫です」
「そう」
スマートフォンを伏せつつ言うと、口元に笑みを含ませた男が、意味有り気な動きで、月影の髪を一束掬ってすぐに手離した。お互いに分かる程度の誘致を含ませた、だが傍から見て不自然でない程度の仕草だった。
「妬けちゃうな。とても可愛い顔で画面を眺めていたから」
紳士然としたた佇まいの中に、隠しきれぬ情欲を燻らせて見下ろして来る瞳。言葉。それを向けられた途端、自分の中でぱちんと音がして、普段とは全く別のスイッチが入ったのを感じた。
「……こういう事をするのは、貴方だけですよ?」
首を傾けて、うっとりとした笑顔を向けて言葉で擽れば、相手からはあからさまに嬉しそうな気配が返ってきた。腕を手のひらが滑り下り、手の甲を包まれて、指同士が絡み合う。「行こうか」男に誘われ、人気のないエレベーターに乗り込んだ。
「ん」
扉が閉まり、最上階のボタンを押すなり、男は月影を抱き寄せて唇を重ねてきた。水音を立てて口内を貪りつつ、腰元をまさぐる手が尻まで下りていき、性急な動作で丸みを鷲掴みにする。
「ぁっ、ん……だめ、せめてお部屋に着いてから……っ」
「あんな物欲しそうな目で誘っておいて、そんなの通らないよ」
密着する下腹部が硬くて熱い質量を感じ取り、これから起きる事を改めて予感して、ぞくりと背筋が戦慄く。思わず瞳を潤ませてしまう月影の耳たぶを、興奮をむき出しにした呼気が擽った。
「今夜もたくさん可愛がってあげるからね……」
ラウンジでの態度とは一転。隠そうともしないぎらぎらとした性欲が、じっとりと体中に絡みついてくるのを感じる。その扱いにひどく充足感を覚えてしまい、人知れず口角が持ち上がった。
(ああ、堪らない)
男に性欲の対象として見られて女のように扱われる事が、今この瞬間だけは、酷く心地が良かった。
昔から、自分の容姿と色気が大嫌いだった。
その目がいけない。誘ったくせに。物欲しそうな顔をして。表情がいやらしい。そんな言葉を何度かけられた事か分からない。
児童養護施設の職員に悪戯された。養子縁組を希望していた男に体を求められた。その妻からは泥棒猫と罵られた。街角で突然男に値段を聞かれた。アルバイト先のオーナーに金を握らされ、ホテルに連れ込まれそうになった。
そんな事が起きる度に、強く願っていた。「お願いだからもうこっちを見ないで」と。
だけどその一方で、自分の性質を隠し続ける事に疲れ果て、今日のように一時の愛情を貪って心を満たすための道具としてそれを使っている。いっそ清々しいまでに矛盾していると思う。だが、どう修正をかければいいのかなんて、もう考えたくもなかった。
穴の開いた器には、何を注いだ所で、どれだけ注いだ所で、中身は瞬く間に零れ落ちていく。そこにまた、手軽に得られる気持ちのいい何かを注ぎ続けるのだ。そう、終わりの無いラットレースのように。
自分でも分かっている。
逃げているだけだ。目を逸らしているだけだ。自分が何より大切にすべきものなんて、分かり切っているのに。こんな事をしているぐらいなら、他に出来る事もあろうというのに。それを差し置いて非生産的な逃避行動に溺れる事で、あの人が居なくなったという事実から、父親という責任から、この、消化しようにもしきれない、胸の中に居座る鉛のように鈍重な虚無感から、逃げているだけだ。
でも……
一時でも目を逸らさないと、それこそ何より大切なものから本当の意味で逃げて、無責任に、首を搔き切って死んでしまいそうだった。
自分一人だったらそうしていた。影縫が居るからこそ、今、自分は生きている。影縫に生かされている。
真綿で撚ったようなか細い糸で、この世界に繋ぎ止められている。









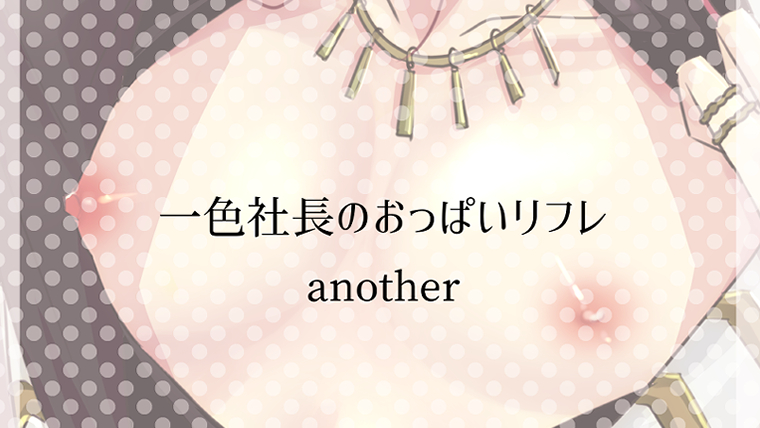
横長.png)

