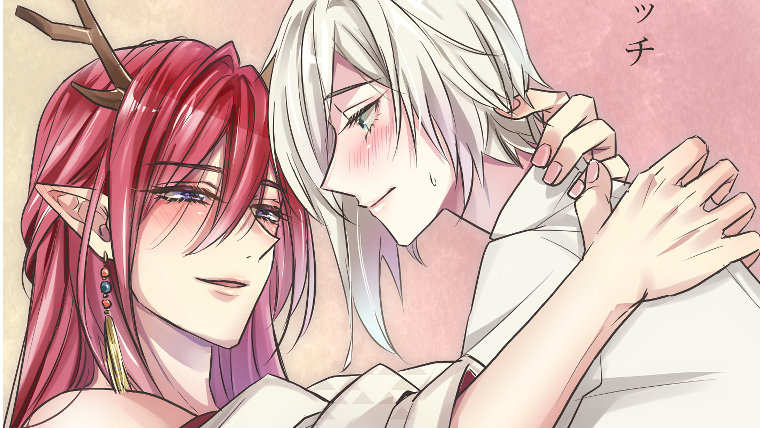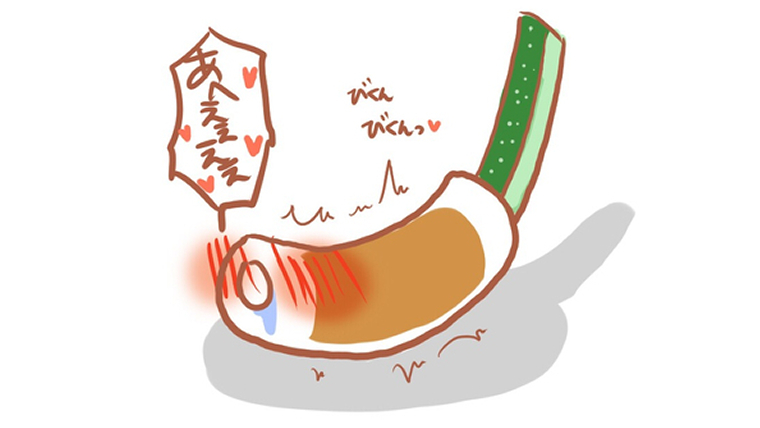父さんのおっぱいを吸わないと出られない部屋に閉じ込められたから仕方ない。
健全な父の日。
「わ、万年筆!」
今しがた届いた息子からの郵便物。それを開封した月影から、嬉しそうな声が聞こえてきた。武蔵もそれにつられて顔を上げる。
月影の手には、ダークブラウンの胴軸に、ゴールドのクリップと天冠の万年筆が握られている。柔らかい印象のそれは、彼の雰囲気とよく馴染んでいた。
「へぇ。いいじゃないっすか」
「ふふふ」
本日は六月の第三日曜日。毎年この日になると、影縫と仁亜から、なかなかに趣味のよい月影好みの贈り物が届くのだ。
「ちなみに~……」
ご機嫌な月影が、再び箱の中へと手を伸ばす。じゃん、と効果音をつけながら取り出されたのは、文字なのか記号なのか咄嗟に判断に苦しむ字体で、「じいじへ」と書かれた大きな封筒だった。
「夜風君からのお手紙も入っていました!」
「えー。月影さんばっかズリィなぁ……」
「しかも二通! ひとつは武蔵君宛てみたいですよ」
「まっじで!?」
どうやら重ねて隠していたらしい二枚目の封筒をスライドさせ、武蔵へと披露する月影。途端武蔵の目が輝き、勢いよく立ち上がった反動で椅子が非難がましい音を立てる。こちらの封筒にもまた独特の字体で、「むさしくんへ」と大きく宛名が書かれていた。
「うわマジ!? 俺に!? やっべ何書いてくれてんだろー!?」
頬を高揚させ、テンションがカチ上がっている様子の武蔵に、月影からは微笑ましい笑いが零れる。開封すると二つ折りの画用紙が顔を出し、内側には、色とりどりのクレヨンで紙いっぱいに絵が描かれていた。主に丸と四角と線で描かれた加減を知らない筆圧のそれは、どことなく人の形に見えなくもない。教育テレビで紹介されるような、幼児が描いた絵そのまんまである。
そして絵の左上には、おそらく仁亜が代筆したであろう文字で、「また一緒に虫取りして遊んでね」と書かれていた。そして隣にはこれまた仁亜が付け足したであろう「武蔵と虫取りしてる所を描いたらしいです」という注釈が。
「あーもう天才。第二のピカソ」
「私もそう思います」
どこからどう見ても同年代の子供が描く平均的な絵なのだが、二人とも夜風メロメロなためツッコミなど居ない。ちなみに月影の方の画用紙には、武蔵宛の絵と何がどう違うのか分からない人間らしき何かが描かれており、こちらには「じいじだいすき」と、夜風直筆と思しき字が苦戦した様子で記されていた。字数が少なく簡単な分、頑張って書いてみたという事だろうか。何にせよ可愛い。仁亜の注釈がない分、もはや何のシーンを描いたのか全く分からないのだが、それもまた可愛い。夜風なら何でも可愛い。
「そういえば……武蔵君は、父の日に何かしないんですか?」
そうやってひとしきり夜風の可愛さを噛み締めた後、画用紙を大切そうに畳みつつ、月影が武蔵に問いかけた。こちらも画用紙を封筒に仕舞う途中の武蔵が、「ええ?」と困惑した様子で眉を寄せる。
「この年ンなって父の日って……それに離れて暮らしてんのに、今更必要あります?」
「そんな事言って、先月明さんにはプレゼント送ってたじゃないですか」
「あれは向こうが図々しく強請って来たからだよ!」
母の日の少し前の事である。明から武蔵へと電話がかかってきたのだ。その内容はといえば、チケット争奪戦が凄まじい某国民的アイドルグループのコンサートにどうしても行きたいのだという物。芸能関係者の顧客もおり、業界人に対して顔がきかないワケではない武蔵に対して、コネを使ってどうにかならないかというなかなかに遠慮を知らないオネダリであった。たまたまご本人と直接連絡が取れるレベルの知り合いが居たため、無理を承知で何とかして頂いた。
「オトンは欲しいモンもこれっていうのが思い浮かばへんし……」
「無難にお酒とかどうですか? あっ、私半分出しますから、二人でいいヤツプレゼントしてあげましょうよ」
「んー……でもなぁ。もうエエ年やから、正直あんまガバガバ酒飲んで欲しくないっていうのもあるんすよねぇ」
「ああ……それは確かに」
いくら酔いを知らない肝臓オバケといえども、もう還暦をすぎているのだ。体を大事にして欲しいという武蔵の意見も最もである。
「でも、特に何もなくても、電話の一本でもきっと千尋さん喜びますよ。私も結局の所、贈り物っていうよりは、影縫や夜風君が私の事を考えて、便りをくれるっていう事実が一番嬉しいですから」
「……」
さてその日の晩、月影が入浴中のことである。武蔵は、静かな居間のソファに身を沈め、スマートフォンを眺めていた。液晶画面には、父親の電話番号が表示されている。
(そういうモンなんかなぁ)
昼間の月影の言葉がずっと頭の片隅に引っかかっていた。あれでも一応人の親で、息子を立派に育てたのだ。その口から出ている意見は、あながち的外れでもないだろう。
ただ武蔵としては、何の用事も無しにいきなり父親に電話をかけるというのが、柄では無いし何だか気恥ずかしかった。これが母親であれば、電話を繋げば後は勝手に喋ってくれるし勝手に喜んでくれるので気が楽なのだが、父親はそういうタイプでもない。果たして間が持つのかという不安もある。
そんな事を考えながら、しばし電話を繋げようかどうしようかと指を彷徨わせていた。だが最終的には、この先親に感謝を伝えられる回数なんて、きっとそんなに多くない。これもいい機会だろう。という結論に落ち着いた。
通話ボタンをタップし、耳に押し当てる。だが武蔵の想いとは裏腹に、待てど暮らせど、聞こえて来るのは延々と続く呼び出し音だった。ちらりと時計に目をやると、時刻は二十時を少し回った所。
(……まぁ、店開けてるんやったら、ちょうど忙しい時間か)
旅館の経営を若い人達に任せるようになった父親は、少しはゆっくりすればいいというのに、今度は自分一人で切り盛りする小料理屋を始めたのである。昔から、忙しい忙しいと愚痴を零していたくせに、結局の所好きで忙しくしていたに過ぎなかったというわけだ。何だそれ。心配して損したわ。この回遊魚が。
ともあれ、夜の営業をしているのであれば、接客だの調理だので手が離せない事も多い時間帯である。それに、いざ電話に出られた所で特に話題も用意していなかったため、出ないなら出ないで良し。そう思った武蔵がスマートフォンを耳から離そうとした所で……ちょうど呼び出し音が止まった。
『もしもし?』
……正直、電話に出られなければそれが体のいい「やらない理由」になったので、むしろ気が楽だったかもしれない。父親の声を聞いた瞬間そわそわと落ち着かなくなってしまい、意味もなくソファから立ち上がる武蔵。
「あー……え? 今電話大丈夫やったん?」
『ああ、今ちょうどお客さん帰られてん。次のご予約の準備しなあかんさかい、時間はとられへんけど。何?』
何? と言われても、特に用事があったわけではない。返しに困り、相手に見えもしないのに、苦し紛れに首裏を掻いた。
「えっと……やっぱ、あんま時間ないなら、ええわ」
『はぁ? なんやねんそれ。用事あるから電話してきたんやろ? 気になるやん』
「いや、特に用事はないねんけど……」
『……は? 用事ないのに俺に電話してきたん? 何で?』
確かにその通りだ。向こうからしてみたら、どういう風の吹き回しかと思っている事だろう。
「その、今日って、父の日やん?」
『……あー……そういえば、せやな』
「せやから……その……いつもありがとう、的な……」
『……』
ぶっ。電話口から、思わずといった様子で笑いが零れる音が聞こえてきた。
『何よいきなり。ありがとうて言われても、もうお前にしてやってる事なんかいっこもあらへんわ』
「まぁ、それはそうなんやけど、でも決まり文句やん。こういう時の」
『取ってつけたみたいな事するなぁ』
「もううっさいねん。欲しがってた息子からの電話やぞ。素直に喜べや」
『うわ、恩着せがましわ~。親の顔が見てみたいなぁ』
「鏡見とき」
字面は皮肉っぽいが、優しい声色が電話越しに滑り込んでくる。分かりづらいのだが、どうやら喜んでくれているらしい。ほっと胸を撫でおろす。
『仕事はどうや?』
「……まぁ、ぼちぼち」
『店屋物以外もちゃんと食うてるか?』
「ちゃんと自分で作ってるって」
『そら感心やわ。月影さんは元気にしてはるの?』
「うん、元気。……今度一緒に、店行くわ」
『はぁ。それはええけど、ウチそれなりに高いで?』
「俺はオトンと違って甲斐性あるんで大丈夫です~」
『……憎らしいヤツやなぁ……もうちょい可愛い事言うならご馳走したろ思たのに』
「残念でした。年寄りは大人しく金払われとき」
『勝手にぐじ丸々一匹仕入れて捌くからな』
「どぉぞどぉぞ。お好きにどーぞ」
『はー。よぉ稼いではるみたいで、羨ましい限りですねぇ』
中学までしか同じ家に住んではいなかったのだが、父親の周りは普段から空気がピリッとしていたのを今でも覚えているし、本気で怒られた時なんてそりゃもう怖いどころの騒ぎじゃなかった。おまけに従業員からは、裏でコッソリ「閻魔様」なんて呼ばれていたりもした。
ただ、もっと昔、自分がまだちょうど夜風くらいの年の頃。微かな記憶ではあるのだが、父親は自分に対してとても優しくて甘かった。ものすごく特別で大切に扱われている。というのは幼心に感じていたし、自分もそんな父親にわざとグズって甘えるのが好きだった。今電話口から伝わってくる空気感は、どことなく、その頃のものと似ている気がする。年を取って丸くなったのか、旅館の経営をやめて肩の力が抜けたのか、それとも自分が年を取って、父親の苦労や愛情というものを、少しは理解出来るようになったからなのか。
自分は今生、きっと「父親」というものになる事は無いけれど、それでも親の想いというものが、少しは分かるようになっていたら嬉しいな。そう思った。
『……じゃあ、ほんまにそろそろ準備しなアカンから、切るわ』
「うん」
『オカンにもたまに電話したりや』
「ええ? オカン話長いし面倒くさいねんなぁ……」
『親孝行やと思ってしたり』
「んー」
『ほなな。……元気そうな声聞けて、良かったわ』
「……うん。なぁオトン」
『?』
「やっぱ……いつもありがと」
『……ふふっ。どぉいたしまして』
◆
オレンジ色の明かりで照らされた石畳の道を、一組の男女が歩いている。一人は仕立てのいいジャケットを着た壮年の男性で、一人は所作が美しく色気のある、夏着物を着つけたお姉様だ。察するに、夜のお店への同伴出勤前、どこかへご飯食べにでも行く所であろう。
大通りから一つ曲がった二人は、ひっそりと暖簾を掲げている小さな飲食店へと入って行った。
「こんばんは~」
「こんばんは」
こぢんまりとした店内は、しかしカウンター席のみをゆったりと設けているために、窮屈な印象を受けない。そしてカウンターの内側では店主が魚を捌いている最中だった。二人の来店に顔を上げたのは、千尋である。
「お越しやす。お待ちしてましたよ」
千尋の店は、一見さんお断りの完全予約制で、メニューは一万円を下らない京懐石のコースのみ。なかなか強気な営業スタイルで客を淘汰しているのだが、それが逆に、富裕層や高い女性を連れ歩きたい客に重宝されていた。大衆酒場にはない特別感と質の良さを求める客も数多く居る。一般人にとっては敷居が高い価格設定も、花街では一種のステイタスであり、必要とされるものなのだ。
「いやー暑い暑い。もう初夏やねぇ」
「この時間になってもまだ外暑いですか?」
「昼間の熱が籠ってしもてんねん。あぁ大将、とりあえずビールね」
「アタシは烏龍茶貰おかな」
「ビールと烏龍茶やね。少々お待ちを。あ、お姉さん、お鞄足元の棚にどうぞ」
「ああ、どーも」
そこでふと、ジャケットを脱いでいた男の動きが止まった。あまり意味も無くニコニコとお愛想しない千尋の、口角が持ち上がっている事に気づいたからだ。
「あれ? 大将今日なんか機嫌いい?」
男に指摘された瞬間、さらに分かりやすく表情を綻ばせる千尋。
「別にぃ? そんな事ありませんよ~?」
「えー!? 絶対機嫌いいって! 何々? もしかして、可愛いおねーちゃん居るお店でも見つけたん? 今度俺にも教えてや~」
「ちょっと! アタシの前でそれ言うってどういう了見してるん!?」
ぱしん。女性の華奢な手のひらが、男の肩を引っぱたく。
「あははっ、冗談やて。俺はママのお店が一番やからな~」
「もう、ほんま余所に浮気したら承知しぃひんからね!」
「あらあら妬けますねぇ。はい。ビールと烏龍茶」
無垢材のカウンターに、コトリと、グラスが差し出される。千尋の表情は、相も変わらず、機嫌の良さそうな笑顔で彩られていた。