ブループリントシンデレラ
一色紅
ずっと憧れていた人と生対面を果たした上、目を見て話まで出来て、何故かオーディションまで合格してしまい、それだけでも理解が追い付かないのに、今俺はといえば、車の後部座席、紅さんの隣に座らされている。間違いなく、今日が人生で一番衝撃的な日になるだろう。
っていか、俺、どこに連れていかれてるの? 空気に飲まれて言われるがままついて来ちゃったけど、本当に大丈夫だった? だってこんなおとぎ話みたいな事普通に考えてありえなくない? まさかこれって何かの罠? もしかしてオーディションっていうのは口実で、新鮮な子供を捕まえて、これから外国的な所に売り飛ばすとか……!?
嫌な妄想を膨らませながらちらりと様子を伺うと、紅さんは煙草を吸いながらスマホを弄くっている。誰かと連絡を取っているようで、メッセージアプリでやりとりする時のポスト音が聞こえてくる。これは……も、もしかして、密売業者と……!?
「あ、あの……」
「ン~?」
あまりの不安に耐えかねて、意を決して声をかければ、どうやらやりとりに意識が向いているらしい生返事が返ってきた。
「俺……今からどこに行くんでしょうか……?」
「……あ? 言わなかったっけ? ヘアサロン」
「へぁっ?」
誘拐の線を疑い始めていた俺にとって、返ってきた目的地はあまりに平和だった。
「ヘアサロン……?」
「そ。ヘアサロン」
「……なんで?」
「だっておめー、髪染めてんだろ? まずはそれ抜かにゃ話にならんでしょうよ」
「……」
真意が把握出来た瞬間に、ずるずると肩の力が抜けていき、「良かったぁ」と、思わず安堵の溜息が零れてしまう。するとそれを聞きつけた紅さんがスマホから目を離し、面白そうに歯を覗かせた。
「何? もしかして誘拐でもされると思った?」
「ぁ……えっ、と……なんかこのまま変なとこに、売り飛ばされるのかなって……」
「あははっ!! バッカじゃねぇの~? ショタコンの金持ちに売り飛ばすならテメェじゃデカすぎんだろ。せめて小学生に戻って出直してきて下さ~い」
「え゛ッ……!? や、や……やっぱり普段は売り飛ばしてるんですか……!?」
「……ぶっ……あーーーーッはっはっはっはっはっは!! っく……ちょっ……マジでっ、やめて……あっはっはっはっは!! 腹イテェ~~~~~!!」
紅さんは、俺の思考回路にシートを引っ叩いて息を切らす程の大爆笑。ひとしきり身悶えた後、目尻に浮かんだ涙を拭いながら身を起こした。
「え? お前わざわざオーディション勝ち上がってまで会いに来る程大好きなアイドルを奴隷商か何かだと思ってんの? エキセントリックすぎねぇ?」
「いや……なんか……うまい話すぎて実感がないっていうか……今こうやって話してるのも、正直、夢かなって……」
「抓ってやろうか?」
「いいです! なんか痛そう!!」
ニタニタしながら伸ばされた指は加減を知らなそうな感じがして、俺は両頬を包んで丁重にお断りした。それに対してまたも笑い声が響いた後、ややあって車内には静けさが戻ってくる。
(……ん?)
っていうか……
この状況を受け止めるのにいっぱいいっぱい過ぎて、大事な部分をスルーしちゃってたけど……
この人さっき、俺の髪の色抜くとか言ってなかった……!?
「ちょっと待って下さいッ!!」
「うおっ!? 今度は何だよ!?」
あまりの動揺に、俺は相手が憧れのトップアイドルだという事も忘れて掴みかかった。
「さっき、俺の髪の色、抜くって言いましたよね!?」
「は? 抜くけど?」
「何で!?」
「はぁ? だってそんな似合わねぇ色とっとと抜いて地毛に戻した方がいいだろ。お前アイドルになる自覚あんの?」
アイドルになる。色んな事が起きすぎて整理がついていなかった俺に、全く真実味のない現実が、改めて突きつけられた。
アイドルに、なるの? ほんとに? 俺が?
「お……おれは……紅さんに会いたかっただけで……アイドルになるとか、そういうのは……あんま、考えてなくて……」
「上~等~じゃねぇかよ。アイドルになりたいです! って鼻息荒く突進してくる猛者共押しのけて、俺に会いたいって気持ちだけでテメェは審査を勝ち上がりそして俺の目に留まった。しかもこんっなクソ似合わねぇ髪の色で自分らしさを隠してんのにだ。それがどんだけスゲェ事か、お前自分がした事分かってる?」
そう言うや否や、紅さんは突然俺の手を絡め取り、さらに顎を持ち上げてきた。
「運命って信じるか?」
「へっ……!?」
その状態でいきなりのドラマみたいなセリフ。間近に迫った瞳は爛々と輝き、瞳孔が細く収縮しているようにも見えた。
「あの瞬間、これはテメェを見つけるためのオーディションだったんだって確信した。俺ァ頭じゃなくて下っ腹で判断するタイプでね。テメェの口説き文句、すっげぇ良かったぜ。正直濡れた。引退して以来久しぶりにゾクゾク来た……♡」
「えっ、ぬれ……えぇっ!?」
「周りにこびりついてる余計なモン全部引っぺがして、素っ裸になった時のテメェの色は、どんっなにか綺麗なんだろうなぁ……。想像するだけで熱くなるぜ。こんっな特大サイズのダイヤモンド見つけちまったらよぉ、最終選考に残ったその他全員がただの石ころに見えて来らぁ」
腰が抱き寄せられ、指の股同士が組み合わされ、顔が間近に迫ってくる。紅さんが唇を舐めると、ちろりと覗いた真っ赤な舌の先っちょに、金色のピアスが刺さっていた。一連の光景と妖しい空気のせいで、緊張とは別のドキドキがお腹の辺りに広がっていく。これっ、なんか……えっ、ち……!!
「……俺をその気にさせたんだ。しっかり責任取れよ?」
ふ、と、目元が可笑しそうに細められた。たちまち紅さんの表情は元通りになり、体温が離れていく。気づけばいつの間にか車は止まっていて、どうやら目的地に到着したようだ。
運転手さんが素早く後部座席に回ってきてドアを開き、紅さんが降車する。「何ぼさっとしてんだ。とっとと降りろ」どぎまぎして動けなくなっている俺を、そうさせた張本人が理不尽に急かした。
「は、ぃ……」
どことなく肩透かしを食らったような気分のまま、俺も大人しく車を降りた。



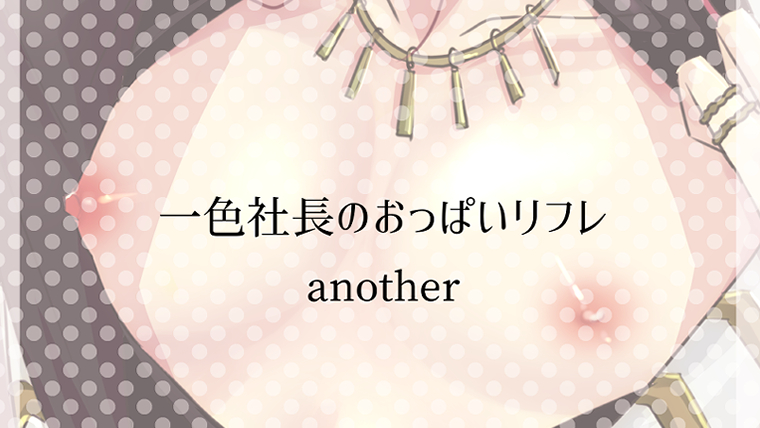





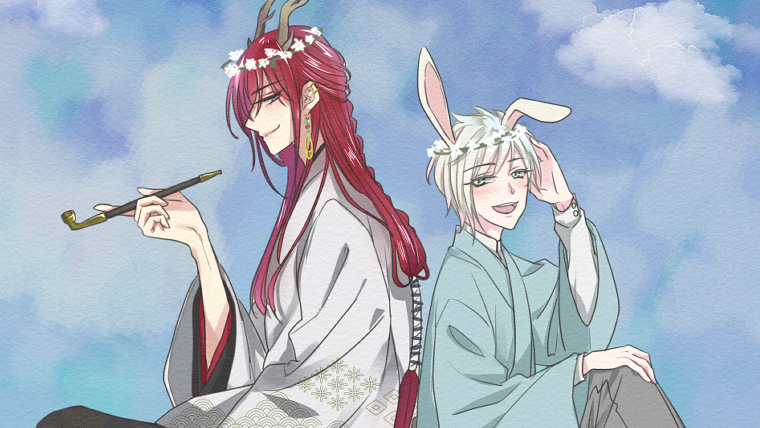
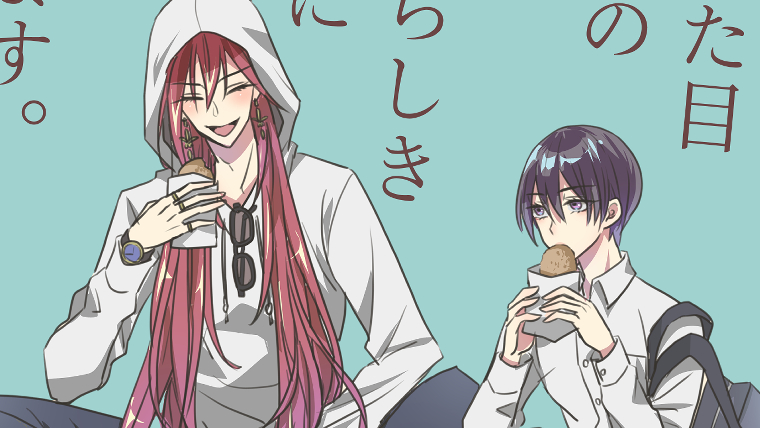

横長.png)